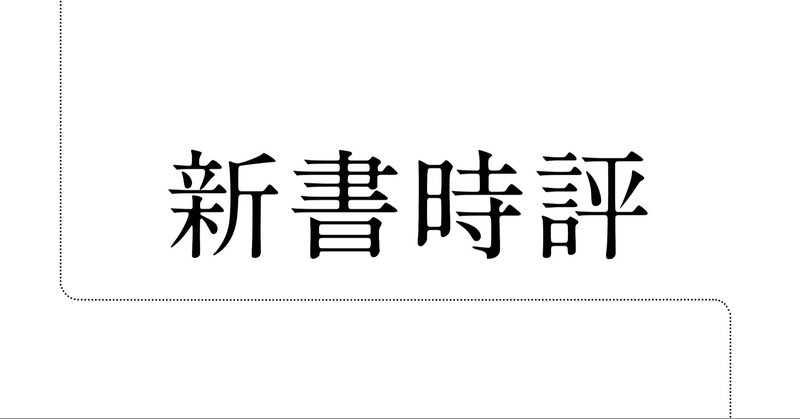
武田徹の新書時評|香港は一冊の難解な書
評論家・専修大学教授の武田徹さんが、オススメの新書3冊を紹介します。
先の6月30日、香港国家安全維持法が施行された。「反政府活動」をした者に無期懲役刑までが科される厳しい法律は自由都市・香港の息の根を止めてしまうのか。
香港は一冊の難解な書だ――。中央政府駐香港連絡弁公室主任を務めた姜恩柱が残した言葉だという。確かにアジアでもあり、ヨーロッパでもあり、一地域でありながら、ひとつの国のようでもある香港は一筋縄ではいかない。倉田徹・張彧暋『香港』(岩波新書)はそんな香港の難解さを読み解こうとする。在香港日本国総領事館勤務後、今は立教大で教える倉田は植民地時代の香港の自由が人権思想に支えられたものというよりも「政府から距離を保」ち、「放置される」なかで育まれたものだという。それは一時の主輸出品だったホンコンフラワー(造花)のように永遠に枯れない確かさを備えていたわけではない。
返還期限が迫るなか、宗主国・英国は区議会設置など自治の定着を図るが時間切れで「上からの民主化」は未完に終わる。そのため返還後の香港人はデモという「下からの民主化」を方法として用いざるを得なくなった。小川善照『香港デモ戦記』(集英社新書)は2019年の「逃亡犯条例」改正反対デモをレポートする。普通選挙の実施を求めて公道を占拠した14年の雨傘運動と異なり、黒装束に黒マスク姿で集合離散を続けるデモのスタイルは包囲網を狭める北京政府への対応でもあった。監視カメラ映像を証拠に逮捕されるケースが増えたから素性を隠す必要が生じていたのだ。
雨傘運動を率いたリベラルな「自決派」に対して今や民族主義的で排外的な「本土派」がデモの主流をなすことも本書で知った。起訴され、本稿が読まれる頃には判決が出ている「民主派の女神」周庭の身を案じるなど日本社会は香港に情緒的に思い入れるが、実情を知ろうとする意欲に乏しい気もする。
香港に生まれて東大の博士課程で学ぶ銭俊華は『香港と日本』(ちくま新書)で本土派の「香港人アイデンティティ」形成において香港住民も参加して日本軍と戦った香港戦と日本占領から英国統治にもどった「重光」の記憶が関与している事情を指摘する。「香港という書」には日本の影も落ちているのだ。日・香の研究者や現地を取材したジャーナリストの仕事を通じてその来し方と今を知ることで、香港の問題が対岸の火事でないと気づく。そして自由と人権を重んじるに至った私たちの歴史の危機として、その行く末を見守れるようになるのではないか。
(2020年9月号)

