
中野剛志「グローバリゼーションの崩壊」アメリカの覇権戦略は破綻、これから日本が進むべき道とは
文・中野剛志(評論家)
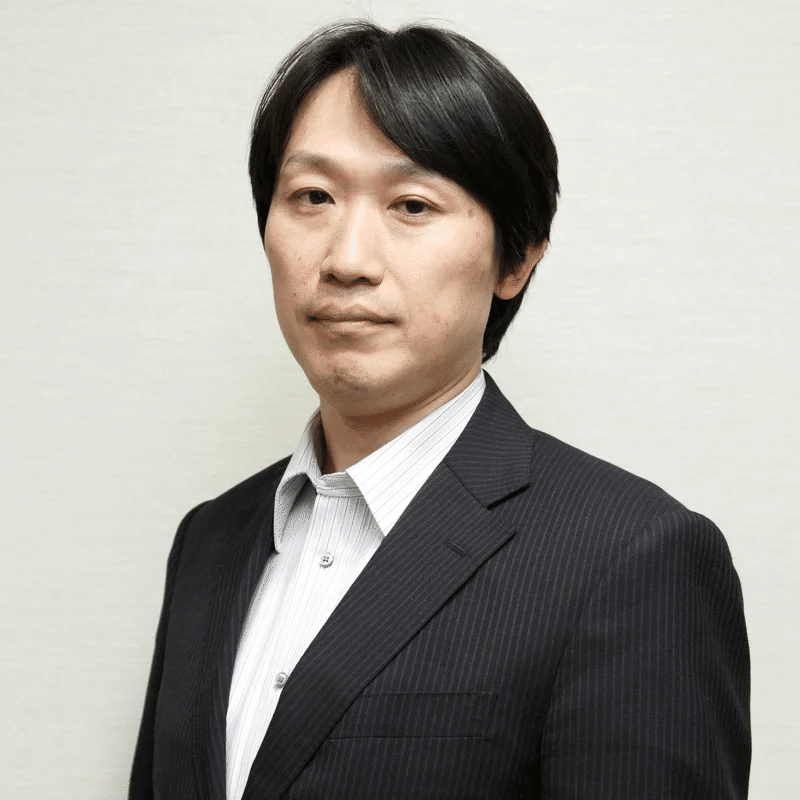
中野氏
「すでに進んでいたグローバリゼーションの溶解」
世界最大の資産運用会社ブラックロックのCEOラリー・フィンクは、3月24日付の株主宛の書簡に「ロシアのウクライナ侵攻で、我々が過去30年にわたり経験してきたグローバリゼーションは終わりを迎えた」と記した。EU(欧州連合)のジェンティローニ欧州委員は4月21日の講演で「この危機(ウクライナ戦争)は、我々の知っているグローバリゼーションの終わりを意味する」と発言した。著名な経済学者ポール・クルーグマンも、ニューヨークタイムズ紙(3月31日付)で、「我々は、1914年(鉄道、蒸気船、電信による第一次グローバリゼーションが終焉した年)の経済的な再現を見ていると言ってよい」と指摘した。アダム・ポーゼンのようなグローバリストの経済学者ですら、ウクライナ侵攻とそれに伴う経済制裁は「すでに進んでいたグローバリゼーションの溶解という巨大なインパクトをもつプロセスを加速させるだろう」と書いている。
我々は、過去30年にわたり、グローバリゼーションを前提としてきた。その前提が崩れた。グローバリゼーションは終わったのだ。ならば、これからの国家政策は、これまでの30年とはまったく異なる、それどころか正反対のものとしなければならないはずだ。ところが、我が国のエリートたちは、この期に及んでもなお「グローバリゼーションは終わった」と認められずにいる。グローバリゼーションを疑ってはならない前提とし、グローバリゼーションへの対応以外の政策を知らずに30年も過ごしてきたものだから、今さらそれを前提にするなと言われても、どうしてよいかわからず、途方に暮れるしかないのだろう。
だが、ロシアのウクライナ侵攻が、突然、グローバリゼーションを終わらせたというわけではないのである。ポーゼンが「すでに進んでいたグローバリゼーションの溶解」と書いたように、グローバリゼーションの終焉は、ウクライナ侵攻の前から始まっていたのだ。

ロシアの侵攻で輸出が止まった小麦
グローバリゼーションは2008年に終わっていた
では、グローバリゼーションの終わりは、いつから始まっていたのか。それは、2008年の世界金融危機(「リーマン・ショック」)である。
グローバリゼーションとは、貿易、投資、人、情報、技術、思想の国境を越えた移動が活発になることであり、その進展は、世界の貿易開放度(世界のGDPに占める輸出入の合計の比率)によって、おおむね計測できる。世界の貿易開放度は、1870年には17.6%だったが、1913年には29%へと上昇した。これが、クルーグマンも言及していた「第一次グローバリゼーション」である。しかし、この第一次グローバリゼーションは、1914年に勃発した第一次世界大戦によって終焉を迎えた。世界恐慌や第二次世界大戦を経て、世界の貿易開放度は1945年には10.1%にまで低下した。第二次世界大戦後、世界経済は再び統合されると、世界の貿易開放度は1980年には39.5%にまで上昇した。1980年代以降は新自由主義(市場原理主義)の台頭によりグローバリゼーションが進められ、1989年に冷戦が終結すると、グローバリゼーションはさらに加速した。2008年の貿易開放度は61.1%にまで達した。この90年代以降のグローバリゼーションは「第二次グローバリゼーション」と呼ばれる。これが、フィンクが「我々が過去30年にわたり経験してきた」と言い、ジェンティローニが「我々の知っている」と言い添えた「グローバリゼーション」のことである。
振り返ってみれば、2008年はグローバリゼーションのピークであった。リーマン・ショックがグローバリゼーションを頓挫させたのだ。しかも、それは一時的な断絶ではなかった。リーマン・ショックが収束しても、世界の貿易開放度はかつての水準へと戻らず、むしろ下降した。2019年の世界経済の成長率は、ついに2008年以降最低の水準にまで落ち込んだ。この現象は、「スローバリゼーション(グローバリゼーションの鈍化)」と呼ばれている。ウクライナ戦争は、すでに進んでいたスローバリゼーションに追い打ちをかけたに過ぎない。だから、仮にウクライナ戦争が終結したとしても、「我々が過去30年にわたり経験してきたグローバリゼーション」は戻ってこない。それは2022年ではなく、2008年にはすでに終わっていたからだ。
アメリカのリベラル覇権戦略から始まった
では、「我々が過去30年にわたり経験してきたグローバリゼーション」は、どのようにして始まり、そして終わったのか、振り返っておこう。
1989年にベルリンの壁が崩壊して冷戦が終結し、1991年にはソヴィエト連邦が解体された。すると、アメリカは、世界の単独の覇権国家になったと信じ、その比類なきパワーによって、リベラルな国際政治経済秩序を建設しようと企てた。このポスト冷戦のアメリカの戦略は、「リベラリズム」という理論に基づいていた。
ここで言う「リベラリズム」とは、アメリカの国際政治経済学の二大潮流のうちの1つの理論を指す。ちなみに、もう1つの潮流は、「リアリズム」と呼ばれている。
「リベラリズム」とは、簡単に言うと、民主主義や貿易の自由などの普遍的な価値観を広め、国際的なルールや国際機関を通じた国際協調を推し進めれば、平和で安定した国際秩序が実現するという理論である。例えば、民主国家の国民は戦争に反対するから、民主国家同士は戦争には踏み切らないだろう。よって、世界の民主化を進めるべきである。あるいは、自由貿易により各国の相互依存関係が深まった世界では、戦争による貿易の断絶は大きな経済的被害をもたらす。だから、貿易自由化を進めれば戦争は起きにくくなるだろう。これが、リベラリズムの論理である。
ただし、非民主国家の民主化であれ、貿易の自由化であれ、それを推進するには、他国に民主化や貿易自由化を強いる覇権国家のパワーが必要である。また、リベラルな国際秩序や国際ルールを策定し維持するためにも、その守護神としての覇権国家の存在が不可欠だ。こうしたことから、リベラリズムは、その理念を実行する段階で、ほぼ必然的に覇権国家と結びつき、「リベラル覇権戦略」のかたちとなって現れる。
アメリカは、ポスト冷戦の戦略として、このリベラル覇権戦略を採用したのである。それが特に顕著になったのは、1997年の第二次ビル・クリントン政権からである。当時の国務長官マデレーン・オルブライトは、アメリカを「不可欠な国(indispensable nation)」と誇らしげに呼んだ。アメリカの覇権的なパワーを使えばリベラルな世界を実現できると信じたオルブライトたちは、コソヴォ紛争に積極的に介入し、NATO(北大西洋条約機構)の東方拡大(東欧諸国のNATO加入)を推し進めた。経済的にも、アメリカは貿易や金融の自由化などを推進し、中国のWTO(世界貿易機関)への加盟を後押しした。「第二次グローバリゼーション」は、こうして始まったのである。
「自由貿易が戦争を抑止する」というお伽話
グローバリゼーションというのは、一般に信じられているように、歴史の潮流や市場経済の原理によって自然発生的に起きるのではない。それは、国家の政治的意志に基づく戦略の産物なのだ。19世紀後半からの第一次グローバリゼーションは当時の覇権国家である大英帝国なしにはあり得なかった。それと同様に、1990年代以降の第二次グローバリゼーションは、ポスト冷戦のリベラル覇権戦略をとったアメリカが創造したものだ。
過去30年間、アメリカの歴代政権は、民主党か共和党かを問わず、リベラル覇権戦略を踏襲し、推進してきた。そのリベラル覇権戦略を基盤として、グローバリゼーションもまた進展してきた。
しかし、アメリカのリベラル覇権戦略の基礎にあるリベラリズムの論理は、リアリストたちが批判したように、最初から破綻していたのである。
例えば、リベラリズムは、世界が民主化すれば平和になると想定している。しかし、歴史的に見て、民主国家であれば戦争を起こさないなどとは言えない。また、非民主国家を民主化するのは極めて困難な作業である。それゆえ、非民主国家に民主主義を押し付けると、かえって秩序のさらなる不安定化を招く可能性が高い。
自由貿易による経済的相互依存が戦争を抑止するなどという話も、歴史によって反証されたお伽話に過ぎない。例えば、20世紀初頭、イギリスとドイツは高度な経済的相互依存関係にあったにもかかわらず、第一次世界大戦に突入した。あるいは1930年代、日米関係は悪化していったが、日本のアメリカへの輸出は1941年までほとんど影響を受けなかったのだ。
そして、リベラリズムがはらむ最大の問題は、アメリカのパワーを過大評価したところにあった。リベラルな世界秩序を構築・維持するためには、民主化や貿易自由化といった政策を押し付けたり、リベラルな国際ルールの策定・維持を主導したりする覇権国家の強大なパワーが不可欠である。1990年代初頭、アメリカは、ソ連の崩壊により、一極主義的な覇権国家になったと錯覚した。しかし、実際のアメリカには、そこまでの強大な覇権的パワーはなかった。にもかかわらず、リベラル覇権戦略によって世界中に手を伸ばし過ぎれば、いずれ疲弊して、アメリカは衰退してしまうだろう。いわゆる「オーバー・ストレッチ(過剰拡張)」論である。要するに、リベラル覇権戦略は、自己破壊的だということだ。リアリストたちは、このようにして、ポスト冷戦のアメリカのリベラル覇権戦略を批判してきたのだが、いかんせん少数派に過ぎなかった。彼らの警鐘は、アメリカの主流派のエリートたちによって黙殺されてきた。

増強される中国軍
中国の民主化を信じていたアメリカのエリート
ところが、アメリカのリベラル覇権戦略は、リアリズムの理論通りに、次第に破綻していったのである。例えば、ジョージ・W・ブッシュ政権は、2003年、イラクや中東の民主化を掲げて、イラク戦争を引き起こした。しかし、その結果、中東はパワー・バランスが崩れてかえって混乱し、民主化どころではなくなった。そして、中東の泥沼に引きずり込まれたアメリカは、著しく疲弊した。ちなみに、ジョン・ミアシャイマーやスティーブン・ウォルトといったリアリストたちは、イラク戦争に強く反対していた。
また、冷戦終結後のアメリカは、中国のWTOへの加盟に協力した。中国をリベラルな国際経済秩序に組み入れ、その恩恵を享受させれば、中国は、リベラルな国際経済秩序を尊重するようになる。中国は経済発展を遂げ、平和的に台頭するだろう。そして、いずれは民主化するに違いない。リベラリズムを信奉するアメリカの主流派のエリートたちは、本気でそう思い込んでいた。
これに対して、リアリストたちは、中国は必ずアメリカと衝突すると警告していた。例えばミアシャイマーは、2001年に発表した『大国政治の悲劇』の中で、大国というものは、自国の安全保障を確保するために、地域内にライバルのいない「地域覇権国」となることを目指して勢力を拡大する、と論じた。この理論に従えば、今後、リベラリズムが期待するように、中国が平和的に台頭するようなことは、およそあり得ない。中国は、必ずや東アジアにおける地域覇権国を目指すであろうし、その障害となるアメリカや日本との衝突は不可避である。ミアシャイマーは、20年ほど前からそう予測していた。2010年には、アメリカ海軍大学教授のトシ・ヨシハラとジェイムズ・ホームズが『太平洋の赤い星』を著し、中国はグローバリゼーションによって平和的になるのではなく、逆に海軍力を拡張していると警鐘を鳴らした。その翌年には、国際政治学者のアーロン・フリードバーグが『支配への競争』を発表し、中国とアメリカがアジアの覇権を巡って争うという予測を示した。
中国に関してリベラリズムとリアリズムのいずれが正しかったのか、我々はすでに知っている。2001年にWTOに加盟した中国は、2000年代、年率10%以上の成長率でGDPを拡大させ、同時に、そのGDP成長率を上回る比率で、軍事費を増加させ続けた。そして習近平政権は、中国が経済発展とともに民主化するというリベラリズムの期待を見事に裏切って、権威主義体制を強めるに至ったのである。
ところが、バラク・オバマ政権下のアメリカは、2010年から17年まで、軍事費を削減し続けていた。2015年に至ってもなお、オバマ政権の「国家安全保障戦略」は、「合衆国は、安定的、平和的、繁栄した中国の台頭を歓迎する。我々は、両国国民に利益をもたらし、アジアそして世界の安全と繁栄を促進するような、中国との建設的な関係の発展を追求する」などと書いていた。
その結果、アメリカと中国の軍事費の比率は、2000年には11対1もあったのに、2012年には5対1にまで縮み、さらに2019年には3対1にまで迫った。この「3対1」という比率を見て、アメリカの優位は揺らいでいないなどと解釈してはならない。地政学的に言えば、東アジアのパワー・バランスを崩すのには、この比率で十分なのである。なぜならば、アメリカは太平洋を越え、あるいはグアムや沖縄など点在する基地から戦力を投射しなければならないが、中国は自国の周辺に戦力を展開すればいいだけだからだ。また、アメリカはヨーロッパや中東などグローバルに戦力を展開しなければならないが、中国は東アジアに集中できる。しかも、アメリカにとっての最重要地域は西半球であるが、中国にとっての最重要地域は東アジアであるから、中国の方がアメリカよりも高いリスクとコストを負う用意もある。よって、東アジアのパワー・バランスは、すでに中国優位に傾いているのだ。実際、軍事力に自信をつけた中国は、台湾併合への野心を鮮明にし、東シナ海や南シナ海において周辺国との領土紛争を繰り返すようになった。
このため、アメリカは、2010年代後半から中国の台頭に対する警戒をあらわにし、対決姿勢を鮮明にするようになった。2018年、アメリカ議会の諮問による国防戦略委員会の報告書は、もし米中が台湾を巡って交戦状態になったら敗北するだろうと警告した。2020年のアメリカ国防総省の年次報告は、中国の軍事力が、すでにいくつかの点においてアメリカを凌駕していることを率直に認めた。その翌年の3月9日、米インド太平洋軍のフィリップ・デイヴィッドソン司令官は、上院の公聴会で、今後6年以内に中国が台湾に侵攻する可能性があると証言した。さらに、彼の後任のジョン・アキリーノは、上院の指名承認公聴会で、中国による台湾侵攻は、大半の人々が考えているよりもはるかに切迫していると述べ、デイヴィッドソンよりもさらに強い危機感を表明したのである。
しかし、イラク戦争以降の中東の混乱で疲弊しきったアメリカ国民は、著しく内向きになっていた。ユーラシア・グループが2019年に行った世論調査によると、「近年の中国のパワーの著しい増大に対して、アメリカの対中政策はどうあるべきか」という問いに対し、「アジアの軍事プレゼンスを削減すべき」という回答が6割近くとなり、特に民主党支持者に多かったのである。
ここから先は

文藝春秋digital
月刊誌『文藝春秋』の特集記事を中心に配信。月額900円。(「文藝春秋digital」は2023年5月末に終了します。今後は、新規登録なら「…

