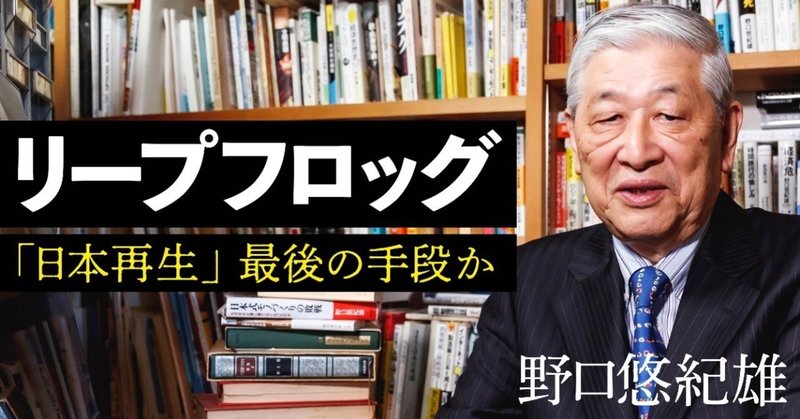
日本は、かつて世界の最先端にいたために遅れた/野口悠紀雄
★前回の記事はこちら
※本連載は第13回です。最初から読む方はこちら。
1980年代、日本は世界の最先端にいました。それは当時の技術体系とそれに基づく産業構造が、日本社会の特性に合っていたからです。
しかし、その後技術体系が大きく変化し、日本の体制は変化を阻害しました。
◆成功は失敗の元
中国で新技術の導入が顕著なのに比べて、日本の立ち遅れが目立ちます。
なぜなのでしょうか?
1980年代には、日本は技術面で世界の最先端にいると思われていました。
「それにもかかわらず、なぜいま遅れてしまったのか?」と、一般には考えられています。
しかし、これまで述べてきたリープフロッグのメカニズムを考えると、「それにもかかわらず」ではなく、「そのために」と考えることができるのです。
つまり、「1980年代には、日本が技術面で世界の最先端にいた。まさにそのために、現在の日本は中国の後塵を拝する結果になってしまった」ということなのです。
こうなるのは、1980年代以降に技術体系が大きく変化したからです。
現在の日本は、「新しい技術体系を採用する能力がないから遅れている」のではなく、「古い技術体系で社会が作られていて、それが固定化してしまっているために、新しい技術を取り入れられない。だから遅れた」ということです。
中国で起きていることを逆転すると、それが日本の姿になります。
「失敗したから成功した」のが中国です。これは、「失敗が成功の元」の例です。
それに対して、「成功したから失敗した」のが日本です。これは 「成功が失敗の元」ということになります。
◆1980年代、日本は世界のトップにいた
1970年代の石油ショックによって欧米諸国の経済が見る影もなく沈滞するなかで、日本の経済力は日増しに増大しました。
日本の一人当たりGDPは、1981年にドイツを、83年にイギリスを抜き、87年にアメリカを抜きました。
80年代末にアメリカで刊行され、日本でも翻訳された『Made in America―アメリカ再生のための米日欧産業比較 』( 1990年、草思社)という本を見ると、この当時のアメリカ人の考えがよく分かります。
これは、MIT(マサチューセッツ工科大学)の産業生産性調査委員会によって書かれた報告書です。ノーベル経済学賞の受賞者であり経済成長論の権威であるロバート・ソローが副委員長。
本報告の基本的結論は「アメリカ企業も日本企業のようにならなければならない」ということです。
日本では、巨大で垂直統合した企業による生産がなされる。企業は銀行と株式の相互保有も含めた密接な提携関係にある。また、終身雇用的雇用慣行が転職率を低くしている。このため、長期的なマーケットシェアの極大化をめざした長期戦略をとり、生産性が高くなる、というのです。
そして、アメリカ産業が弱体化した理由として、「シリコンバレーでベンチャーキャピタルが登場し、アップルのようなおかしな企業を助けている。優秀な技術者が古い企業からアップルに移り、アメリカのこれまでの優秀な企業(大規模で成熟した企業:モトローラ、フェアチャイルドなど)がダメになる」としています。
◆モノづくりが産業の中心だった
60年代頃までの技術体系では、製造業、なかんずく、鉄鋼業のような重厚長大型装置産業と、自動車のような大量生産の組立て産業が中心産業でした。
この当時、アメリカにおいても、製造業が経済全体の中で重要な役割を担う産業でした。
それが日本からの輸入の洪水によって衰退しつつありました。
この報告書は、アメリカ製造業の生産性低下に警鐘を鳴らし、その復活を望んだのです。
危機感が持たれたのは、製造業中心の産業構造が変るとは考えられていなかったからです。
本書はつぎのように主張しています。
「製造業からサービス産業への転換は、国民経済の発展の過程として避けることのできない道であり、同時に望ましい過程であるという見方が行なわれている」。
しかし、「われわれは、この考え方は間違いであると考える。アメリカのように巨大な大陸型経済は、将来とも、サービスの生産者として機能してゆくことは不可能であろう」
そして、「アメリカは、世界の市場において、引続き製造業の分野で競争していく以外に選択の余地はない」と結論しています。
その理由は、「商品の輸入のためにサービスを輸出しなければならないという姿は現実的ではないということである」。
「サービス化はありえない」、「モノづくりこそ生きる道」というのが、本書の基本的認識だったのです。
◆日本の仕組みが適していた
この当時の技術と産業を前提にすると、日本の社会構造がそれにうまくフィットしていました。
独創性や創造力というよりは、確立された技術で効率よく仕事を進めることが重要でした。そのためには、協調して仕事をするという日本の仕組みのほうが向いていたのです。
この報告は、「アメリカでは、企業内の個人とグループの相互関係、企業と供給業者の関係などにおいて、協調が欠けている」と指摘しています。
教育の仕組みもそうです。
この報告は、アメリカの教育システムには問題が多いとしています。
まず、初等・中等教育に問題があると指摘します。さらに、仕事に必要な特殊技能の大半を正規の教育機関で教えるアメリカ型のシステムと、日本のようにオンザジョブ・トレイニング(OJT)を比較し、後者のほうが優れているとしています(実際のところは、大学研究室の基礎研究から生まれた新技術がその後の世界を変えたのですが)。
◆情報通信技術に大きな変化があった
1980年代以降に、大きな変化が起きました。
第1は、先進国の中心的産業が製造業から情報通信へと転換したことです。これは、中国をはじめとする新興国が工業化に成功し、安い労働力で生産が可能になったことによります。
アメリカは、この条件変化に対応して脱工業化を果たし、生産性の高いサービス産業を成長させました。アメリカは、この報告が望んだ「製造業の復活」という方向とはまったく逆の方向に進み、そして史上空前の大繁栄を実現したのです。
第2は、情報通信の技術の中で生じました。
それまでの大型コンピュータを中心とする集中型の仕組みから、PCとインターネットを用いる分散型の仕組みへ、さらにクラウドコンピューティングへという変化です。
大型コンピュータを中心とする情報処理の仕組みは、日本の社会構造や企業構造にあったものでした。しかし、分権的性格を持つITには対応できないのです。そして、全てを自社内で処理しようとするために、クラウド化も進みません。
◆企業も教育も変われなかった
変化に対応して、企業も教育も変わらなければなりませんでした。
しかし、日本では、それが出来ませんでした。
古い技術体系に即した社会システムが強固に出来上がっていたからです。
企業が変われなかったのは、社内に保守勢力がいるからです。過去の成功事業を推進した人々は、その後昇進し、経営方針に強い影響力を及ぼす地位についています。ところが、ビジネスモデルの転換のためには、過去の成功事業からの転換が必要です。それは、それらを推進した人々の存在意義を否定することになります。彼らが新しい事業に反対し、抵抗勢力になるのは、当然のことです。
日本的な終身雇用体制の下では、従業員は一つの企業に一生をかけます。企業は、実質的には経営者と従業員の共同体なのです。したがって、人員整理が出来ません。不採算になった事業や工場を閉じることが必要になったとしても、それが出来ません。
だからビジネスモデルを変えられないのです。
こうして、大部分の日本企業は、環境の大変化に直面しても、そもそも対応しようとさえしませんでした。そして、それまでのビジネスモデルを継続し続けました。
新しい経済活動においては、ルーチンワークを効率的にこなすことではなく、独創性が求められます。したがって、集団主義でなく個性が重要になります。
しかし、教育も創造性を発揮できるようなものに変われません。
こうして、それまでの日本の経済体制は、新しい体系の下では、優位性を発揮できず、むしろ変革と進歩に対して桎梏となったのです。
(連載第13回)
★第14回を読む。
■野口悠紀雄(のぐち・ゆきお)
1940年、東京に生まれる。 1963年、東京大学工学部卒業。 1964年、大蔵省入省。 1972年、エール大学Ph.D.(経済学博士号)を取得。 一橋大学教授、東京大学教授(先端経済工学研究センター長)、 スタンフォード大学客員教授などを経て、 2005年4月より早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授。 2011年4月より 早稲田大学ファイナンス総合研究所顧問。一橋大学名誉教授。2017年9月より早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター顧問。著書多数。
【編集部よりお知らせ】
文藝春秋は、皆さんの投稿を募集しています。「#みんなの文藝春秋」で、文藝春秋に掲載された記事への感想・疑問・要望、または記事(に取り上げられたテーマ)を題材としたエッセイ、コラム、小説……などをぜひお書きください。投稿形式は「文章」であれば何でもOKです。編集部が「これは面白い!」と思った記事は、無料マガジン「#みんなの文藝春秋」に掲載させていただきます。皆さんの投稿、お待ちしています!
▼月額900円で『文藝春秋』最新号のコンテンツや過去記事アーカイブ、オリジナル記事が読み放題!『文藝春秋digital』の購読はこちらから!

