
特別読物 宮沢りえ「彷徨える平成の女神」
「文藝春秋」2019年5月号の「特別読物 宮沢りえ『彷徨える平成の女神』」を特別に公開します。その才能の虜になった人々が明かした30年の波瀾万丈とは。
(取材・文=石井妙子、ノンフィクション作家)
(※年齢・肩書などは取材当時のまま)
平成を代表する女性スター
改元にあたって、平成を代表する女性スターは誰かと考えたとき、彼女の名前が浮かんだ。
宮沢りえ、46歳——。かつては人気や話題性が先行するアイドルスターであったが、近年は女優としての評価を高めた。映画では『紙の月』、『湯を沸かすほどの熱い愛』で各映画賞の主演女優賞を受賞。舞台でも、故・蜷川幸雄や野田秀樹ら一線級の演出家にオファーをされ続けてきた。今秋には蜷川実花の監督作品『人間失格』の公開も控える。
また、昨年には二度目の結婚をし、母として小学生の娘を育てているが、そうした私生活は極力、メディアに語るまいとしているように映る。
彼女は昭和の終わりに登場し、平成を駆け抜け、今の彼女となった。その軌跡を時代の中で振り返りたい。

宮沢りえ
三井のリハウスのCMが始まったのは昭和62(1987)年。バブル期の真っ只中で、「一億総中流」といわれていた頃のことだ。「リハウスしてきた白鳥麗子です」と、たどたどしくセリフを語る少女の、可憐な美貌が話題を呼んだ。「白鳥麗子役の美少女」として、世間はまず彼女を認識したのである。
「宮沢りえ」として知られるようになるのは翌年のこと。映画『ぼくらの七日間戦争』への出演で、顔と名前が同時に知れ渡った。作品は管理教育を強いる教師たちに戦いを挑む中学生11名の物語。意外なことにキャスティングされたのは、三井のリハウス以前であったと監督の菅原浩志は振り返る。
「学級委員役だけが最後まで決まらなかったんですが、約1万2千人の中学生に会い、やっとりえに出会えた。自由の女神のように崇高で、皆が自然と従いたくなるような少女を探していたんです。演技経験はなくても良かった。りえを見た瞬間、『ああ、やっとみつけた!』と感じた。あの透明感。こんなにも清らかに育ってくれた少女がいたなんて」
当時のりえはモデル事務所に所属していたものの、「女優になりたい」といった意志は当人にまったく見られず、映画出演を決めた理由も「中学生時代の思い出になりそうだから」というものだった。
昭和最後の夏休みに公開されると映画は大ヒット。年が明けて平成になり、りえが菅原のところにやってきた。
「突然、りえが『高校1校受けたけど落ちちゃった。私、女優になります』と言い出した。私は映画に抜擢した責任を感じ、『りえ、今からでも行ける高校を一緒に探そう。業界に同じ年の友だちはいないよ。女優になるのはそれからでもいいじゃないか』と説得にかかりました。でも、彼女の決意は非常に固かった。1年前まで女優になりたいなんて、まったく思っていなかった子でしたが」
母・光子との強い絆
りえは高校に行かず、16歳で本格的な芸能界デビューを果たすと、すぐさま映画、テレビ、レコードでそれぞれ大評判となる。何よりも話題をさらったのはカレンダーだった。
ヒップに紐一枚をまいた姿は、「ふんどしルック」と言われ世間を騒然とさせた。昭和のアイドルは清楚、清純、未熟さを売り物にしていたが、そうしたアイドル像をぶち壊すインパクトがあったからだ。未成熟と成熟の合間の危うさ。それに戸惑うような、それを自覚しているような、りえの蠱惑的な表情――。
こうした演出、売り出し方を考えたのは、母の光子だった。その関係を間近で見てきた音楽プロデューサーの酒井政利は、こう振り返る。
「光子さんの娘への愛はとても激しいものだった。光子さんにとって、りえさんは愛する娘であり、表現の手段でもありました」
りえを作ったのは光子だとよく語られる。強烈なキャラクターで知られ、りえへの愛は支配的で狂気を含んでいた、と証言する人も少なくはない。「一卵性親子」と称された母子。「りえママ」と時に批判を込めて、時に称賛を込めて呼ばれた。
私はその「りえママ」こと宮沢光子と一度だけ、電話で話をしたことがある。伝説の銀座マダム、上羽秀(うえばひで)の生涯を描いた私の著書『おそめ』が、もし映像化されるのであれば、是非、娘に主演を務めさせて欲しいと出版社に連絡があり、ちょうど映像化の話が舞い込んできたので、私から「りえママ」に電話を入れたのだ。その際、受けた印象は、巷間言われているとおりで、「ああ、なるほど、これが『りえママ』か」と思わされるものだった。
確かに傍若無人さも感じはしたが、嫌悪感は抱かなかった。それは足元を見られるまい、娘に寄ってくるものには一瞬も気を許すまいとハリネズミのように毛を逆立てる母の姿をそこに見たからである。
この母を知らなければ、「宮沢りえ」は理解できない。
光子は昭和24(1949)年に生まれ、東京で育った。父の喜一は絵描きを目指し、戦後、商業デザイナーに転じて成功する。子どもは5人おり、光子は末子。母が家を出てしまい、途中から父子家庭となる。
光子はバレエを習い、水泳でも才能を見せたが、いずれも父の反対に遭い、本格的に極めることはできなかった。女は家庭に収まるのが一番と考える、保守的な父に光子は反発する。高校を卒業すると家に寄り付かなくなり、容姿に恵まれた光子はモデルやホステスをしながら当時の六本木で遊び、自分にふさわしい人生を自分の手で掴もうとした。
外国で語学を学ぼうとヨーロッパ行きの船に乗り、オランダ人の船員と恋に落ちる。しばらく、オランダの片田舎で暮らしたものの退屈な生活に耐えきれず帰国。昭和48(1973)年4月、りえを東京で出産する。夫が光子を追いかけてきたが、文化の壁は厚く、以後、りえを女手ひとつで育てる。シングルマザーという言葉もなかった時代、母子家庭に世間の風は今よりもずっと冷たかった。
そんな光子を全面的に助けたのが、姉のさつ子だ。夫、息子と練馬区大泉学園に住む主婦のさつ子にりえを預けると、光子は都会にマンションを借り、銀座でホステスとして働いた。さつ子には養育費を仕送りした。やがて、店でピアノを弾いていた小澤典仁と再婚し、りえを引き取る。小澤が当時を振り返る。
「光子は家庭には向かない女性だった。煙草と飲み歩くことが大好きで。酒には飲まれてしまう。りえはかわいかったが、僕には懐かなかった。光子がそう仕向けるからです。僕が何か言った時、りえが泣いて光子に駆け寄った。すると光子が『だから言ったでしょ、パパのそばには寄るなって』と。つねに2対1にされてしまう。りえは離れ離れで育ったせいか異常なママっ子で、光子のスカートの陰に隠れて片時も離れようとしない。光子はりえを溺愛していたけれど、怒る時は激しかった」
夫婦ともに夜の街に働きに行く。りえは家にひとり残される。近所の人が同情して、りえにおにぎりをくれた。それを食べたと知ると光子は激怒した。自分以外の誰かが娘に愛情をかけ、結果、娘がその相手に好意を抱く、それが身を切られるように辛かったのだろう。りえはこうした経験から、いっそう母だけに密着していく。
やがて光子は身ごもり、りえにとっては4歳違いの異父弟を生むが、翌年には離婚する。
光子がりえに自分以外の人間に愛を求めることを許さなかったように、母もまたりえ以外を愛さなかった。小澤側から言い出された離婚の条件を呑み、息子との縁は切った。
離婚後、光子は大病をする。子宮癌だった。幸い手術は成功したが、ホルモンのバランスが崩れ別人のように太った。感情の起伏もまた、いっそう激しくなった。この経験が「若い時の美しさは特別なもの。20歳を過ぎれば、りえも太るかもしれない。私のように」という持論に繋がっていく。
銀座や六本木で働けなくなった光子は、都心から離れたところでスナック勤めをし、保険の外交員になった。そして、キャベツ畑が広がる姉の家近くのアパートに移り住むと、小学生のりえを引き取り、ふたりで暮らし始める。
生活は楽ではなかったが、窮状を救ったのは幼いりえだった。美貌に恵まれた少女は近所に住むカメラマンに声をかけられ、小学5年生の時からモデルを始めた。次々と仕事が舞い込み、小学校は休みがちになる。ここまでが昭和の話である。
一流の男たちとの出会い
平成元(1989)年、りえが区立大泉学園中学を卒業すると、母子は麻布のマンション、そして広尾ガーデンヒルズへと移り住む。生活は一変した。
家庭的でないと思われがちな光子だが、料理の腕前は素人離れしていた。広尾の自宅は光子によって選ばれた「一流」の男たちが招かれるサロンとなった。映画監督、写真家、俳優、イラストレーター、作家。彼らはりえの教師であり、仕事相手だった。サロンに招かれていた菅原は、当時の様子をこう振り返る。
「光子さんが選んだ大人たちの中に、10代のりえも交じっていた。映画監督の勅使河原宏さんも、りえをとてもかわいがったひとりでした。ある時、りえを連れて芝居を観に行き、途中で勅使河原さんは席を立った。『舞台が面白くなければ意思表示する。大切なことだよ』と教えてくれたと、りえは言っていました」
松竹のプロデューサーだった奥山和由もサロンのメンバーであり、りえの主演映画『エロティックな関係』『豪姫』の製作に携わる。
「仕事は全部ママが決めて、何かあればママがクレームを言う。ママを悪くいう人も当然、出て来るけれど、圧倒的な戦闘能力で娘を守っていたんだよね。りえちゃんに対しては無条件の愛だった。『ねえ、最高でしょ』って。事実、最高でした。りえちゃんには、すべてを浄化する力と、全身から発するオーラがあって。一方、ママには芸術的なセンスがあった。ビートたけしに映画を撮らせたらいいと僕に勧めたのもママ。興行的に惨敗して、ママに愚痴を言ったら、『そのうち回収できるわよ』と。実際、そうなった。『その男、凶暴につき』『ソナチネ』など、今では名作として評価されています」
音楽では酒井がプロデュースし、デビュー曲は小室哲哉が作曲。酒井の下でりえを担当した元CBSソニーの髙野利幸はこう振り返る。
「ママは音楽にはかなり厳しかった。洋楽が好きで、ある日、デビッド・ボウイの『Fame』を持ってきて、『これのカバーができないかしら』と言われて。『権利関係を取るの、大変だな』と思ったけれど、何とかクリアして3曲目のシングル『Game』として発表した。この曲で紅白に初出場したんです」
紅白でも光子は天下のNHKを相手にバトルをする。NHKにはりえを行かせない、別の場所からの生中継、演出はこちらの案で、という条件をすべて呑ませた。
光子の剛腕ぶりを非難する声も湧いたが、りえへのオファーは絶えなかった。光子はりえの個人事務所を設立し、姉のさつ子とともに経営した。平成元年の本格的なデビューと同時に、飛ぶ鳥を落とす勢いで国民的スターとなった少女。だからこそ、その日、新聞を開いた人たちは驚愕した。
「ヌードでもどうですか」
平成3(1991)年10月13日、読売新聞に掲載された写真集『サンタフェ』の全面広告。りえは一糸纏わぬ裸体。撮影は篠山紀信。日本中が揺れるような騒ぎとなった。りえは18歳。写真集が作られた経緯を篠山はこう説明する。
「たまたま、りえのいない席でママと世間話になって冗談で言ったんだよね。『そろそろ、ヌードでもどうですか』って。社交辞令だよ。ところが、ママが『そうね、撮るとしたら、連休明けかしらね』って。僕は驚いて後日、改めてオファーした」
計画は極秘で進められ、一行は米ニューメキシコ州のサンタフェに向かった。初日の野外撮影を終えてホテルに戻り、壁にポラロイド写真を張って篠山とりえが見入っていると、そこへ光子がやってきた。
「ママは写真を見て、『あなたたち、何やってるの。こんな写真撮りにきたんじゃないわよ』って怒り出した。初日はほとんどヌードを撮らなかったから。気を遣って。だから翌日から遠慮せず撮りにいったよ」

篠山紀信氏
写真集は155万部を売り上げる。それは芸能界の話題を超える社会現象だった。18歳の少女がヌードになったことを問題視し、光子を「女衒(ぜげん)」とまで非難する声も上がった。主体となったのは父親世代、祖父世代の男性たち。一方、女性たちはおおむね好意的に捉えた。作家、瀬戸内寂聴もそのひとりだった。
「私も買いましたよ、『サンタフェ』。綺麗でした。芸術ですよ。男の人たちが、テレビで勝手なことを言って批判してましたよね。そういう男の人こそ人に隠れてこっそりヌードを見て下品に喜んでいるのよ」

瀬戸内寂聴氏
篠山は光子の決断を、こう見る。
「光子さんはアーティストだったから。りえという存在を使って、作品を残したかったんだと思う。ある局が『サンタフェ』の発売日に写真をバンバン許可なく放映した。その時の光子さんの怒りようはなかったよ。局側は大手プロダクションに所属していないから見下したんだ。あそこは母ひとり、子ひとりでやってるようなところだから、って。でも、ママはひるまず抗議した。『宮沢りえ』の価値を貶める相手には徹底して発言と抵抗をした。よく頑張ったと思うよ」
女性自らが誇らしく肉体をさらす。女の裸身を貶めて性を淫靡なものとする日本の男社会の価値観に、『サンタフェ』は揺さぶりをかけた。だからこそ、保守的な男たちは動揺し、過剰に攻撃したのだろう。
以後、人気女優が次々とヌード写真集を出し、一般の若い女性たちの間でもヌード写真を撮って残す風潮が生まれた。平成は「宮沢りえ」によって作られていくかのようだった。
光子の課題は次に、りえをどうやって大人の女性にするか、に移った。酒井は振り返る。
「ママはりえさんの異性関係までコントロールしようとしました。光子さんには、一流の男性と付き合ってこそ、一流の女性になれる、という信念のようなものがあった」
光子は雑誌『DENiM』に自分が連載するエッセイの中で、りえの目下の恋人はビートたけしだが、ふたりはまだ肉体関係を結んでいない、好きならそうなるのが自然なのにと書き、物議をかもした。ビートたけしには妻子があり、りえより20歳以上も年長である。これをどうとらえていいのか、芸能マスコミに身を置く井上公造は当惑したと振り返る。
「あれもママ一流の演出だったのかもしれません。あるいは、そう書くことで逆にりえさんの清純さを宣伝したかったのか」
だが、19歳になるりえには、当然ながら自我が芽生えており、母親のけしかける恋に乗ろうとはしなかった。「たけし・りえ」と騒がれるなか、ひそかに恋を育んでいく。相手はスポーツ新聞での対談で知り合った相撲界のプリンス、貴乃花(当時は貴花田)。その頃、りえに匹敵する10代のスターは彼だけだった。
街中でデートをして間もなく、貴乃花は、「結婚して欲しい」と切り出し、りえは受け入れる。
「大人ばかりに囲まれ育ったりえさんは、自分と同世代の貴乃花に惹かれていった。住む世界は違うけれど境遇は似ていました。ふたりとも中学を出て特殊な世界に入り、10代で日本を代表するスターになった。常に注目され、大人たちの期待を背負っていたところも一緒でした」(酒井)
平成4(1992)年10月26日夜10時、久米宏の「ニュースステーション」(テレビ朝日)の冒頭で、いきなりふたりの婚約が報じられた。貴乃花が所属する藤島部屋が、懇意にしていたテレビ朝日に特ダネとして情報を流したからだ。日本中に激震が走り大騒ぎになった。雑誌は急遽臨時増刊号が出され、テレビは連日この話題を追い、海外メディアでも報じられた。

現役当時の貴乃花
破談会見の真相
1カ月後の11月27日、ふたりはともにピンク色のキモノに身を包み、手をつないで記者会見に臨んだ。誰が見ても幸福な風景だった。だがこの頃、すでに周囲では波風が立ち始めていた。角界の周辺が、宮沢りえとの結婚を危ぶんだからだ。
一方、酒井は光子の心が麻のように乱れるのを目にしていた。
「さみしかったんでしょう。りえさんは幸せそのもの。愛する人に夢中で自分の声が届かない娘を見るのが光子さんは辛い。恋人と長電話をするりえさんに激高することもあれば、気弱さを見せることもあった。りえさんも、そんなママを見ると不安になり、さびしくなる」
貴乃花の背後には、両親、部屋、後援会、角界が確固としてあった。それは日本の男社会そのもので、光子の価値観とは相容れない。「宮沢りえ」を低く位置づけ、嫁に来たければ仕事を辞めろ、女将さんになる覚悟はあるのか、と迫ってくる。そうした態度が許せない。光子に対する悪意に満ちた報道が続き、無軌道な母が結婚の障壁とまで書かれた。
婚約は2カ月後に、解消される。
翌年、初場所を終えて大関への昇進が決まった1月27日午後、りえと貴乃花は久しぶりに会い、破談を確認する。夕方6時、先に記者会見を開いたのはりえだった。宮沢家と親しかった、スポーツ紙の元記者、神戸陽三が明かす。
「記者会見場をセットしたのは私です。あの時は光子さんも焦っていました。6時からの全国ニュースで中継されることを意識して、貴乃花側より前に記者会見をやったほうがいい、と進言した。『最高のオシャレをしてきてください。泣かないで、しっかりと自分の言葉で話をした方がいい』と、りえさんには光子さんの関係者を通してアドバイスをしました」
りえは、「人生最高のパートナーにはなれなかった。悲劇のヒロインにはなりたくない」と語り、破談の原因は光子かと記者に聞かれると、母をかばった。
数時間後、貴乃花が記者会見を開く。破談を申し入れたのは自分だと語り、記者に理由を聞かれ、「愛情がなくなった」と答えて、「無責任ではありませんか」と責められた。
5月に予定されていた、りえと貴乃花の結婚は流れ、6月、皇太子と小和田雅子さんのご成婚に世間は歓喜した。
この破局から、快進撃を続けていた「宮沢りえ」の歯車は狂い始める。CDは売れず、出演したドラマは振るわず、CMの話は来なくなった。加えてりえは、傍目にも明らかなほど痩せていった。
平成6(1994)年、歌舞伎役者で妻子ある中村勘三郎(当時は勘九郎)との交際が噂されたのは、たけしの時と同様、光子の思惑が働いたからだった。酒井が振り返る。
「勘三郎さんのような男性と付き合うことは、芸の上でも、女性としてもプラスになると光子さんは考えていた。でも、ビートたけしさんの時もそうですが、母親にけしかけられたら、男性はむしろ引きます。りえさんが交際を心から望んでいたのは、勘三郎さんとは別の若い歌舞伎役者さんだった。その人には恋人がいて完全な片思いでした」
片思いの相手、市川右團次(当時は右近)に元モデルの恋人がいると週刊誌に報じられた約10日後、母親と大喧嘩をしたりえは京都のホテルで自殺未遂騒動を起こす。同ホテルに勘三郎も泊まっていたため、大騒ぎになった。
さらに翌年には映画『藏』を突如、降板。浅野ゆう子の次に名前がクレジットされることに対する抗議が理由だと報じられ、一斉にバッシングを受けた。倉本聰脚本「北の国から」では元AV女優の幸薄い女性を演じたが、あまりにも痩せた姿が痛々しかった。
一方、貴乃花は絶頂期にあった。この年の初場所から横綱となり、5月に元人気アナウンサーの河野景子と結婚。9月に第一子を授かった。
昭和から平成の初めまで女性スターは主に女優か歌手だった。だが、平成に入って突如、テレビ局の女性アナウンサーたちがその座を奪い始める。容姿に恵まれ、学歴もあり高嶺の花とされる。その頂点にいた一人がフジテレビの河野だった。
平成8(1996)年1月、りえ親子はひっそりとロサンゼルスに居を移した。酒井は出立を見送った。
「事実上、芸能界を追放されたようなもので、痛々しい旅立ちでした」
「新しい人生を歩みたい」
りえが再び日本に戻り、仕事に本格復帰するのは、平成13(2001)年前後。ちょうど、小泉旋風が吹き荒れ、第一次小泉政権が誕生した頃だ。りえは20代の後半になっていた。
幸先の良いスタートだった。山田洋次監督に抜擢され、平成14(2002)年公開の『たそがれ清兵衛』で日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を受賞する。
翌々年には野田秀樹作・演出の舞台「透明人間の蒸気」に初主演。30歳になっていた。りえとの出会いを野田はこう振り返る。
「人に紹介されてアムステルダムで出会いました。とにかく痩せていて、どうしてだろうって。僕は当時、イギリスにいたし、芸能ニュースには疎かったので、あんまり彼女の事情を詳しくは知らなかった。でも、話してみると、とにかく陽気で面白い子だった。舞台に出てもらったのは、それから3、4年後。華奢で線が細い印象がありましたが、舞台に立つと周囲の空間まで支配してしまうオーラがあった。これは演出して出るものじゃないし、訓練してどうなるものでもない。持って生まれたものです」
野田はその後、主演女優として宮沢りえを使い続け、「圧倒的に信頼している」と話す。
「漢字は読めないんだけれど(笑)、本(脚本)を非常に深く読める。演出家の予想を超える演技で返してくれる」
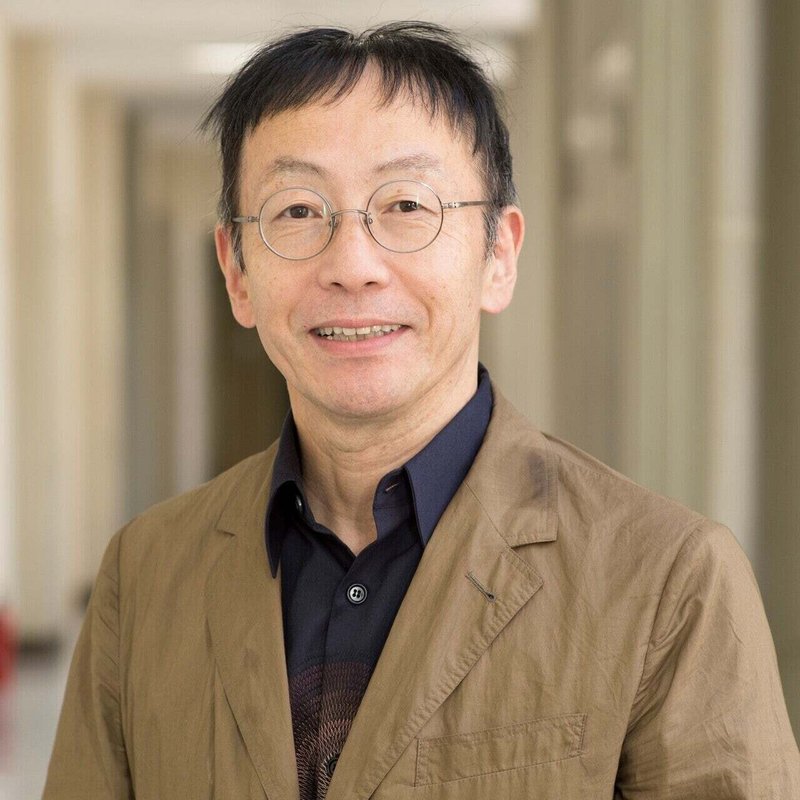
野田秀樹氏
野田や蜷川と親しく、数々の舞台を見続けてきた演劇評論家、長谷部浩の評価も高い。
「声、姿、顔のどれをとっても女優として傑出している。大女優と呼ばれるのも時間の問題だと思います」
更に映画『父と暮せば』で評価され、フジテレビ「女の一代記」シリーズでは、『瀬戸内寂聴~出家とは生きながら死ぬこと』に主演。瀬戸内を演じて評判になった。りえはこの作品に大変なこだわりを見せ、剃髪するシーンでは自分の髪を実際にそり落とすと言い張り、周囲に止められる。
「私をどうしても演じたいっていうんだけれど、美人の作家なんてリアリティがないからダメだって反対した。でもりえちゃんは見事に演じ、作家そのものだった。驚きました」
瀬戸内の生涯をそれほど演じたいと思った理由はどこにあったのだろう。瀬戸内に尋ねた。
「本人に聞いていないからわかりませんが、私は家庭の主婦、小説家、出家者と変化していった。変わりたい、新しい人生を歩みたい、という思いが、当時のりえちゃんにもあったのかもしれません」
話題性や人気がかつての「宮沢りえ」を支えていた。だが、りえはロスでの日々を経て、演技力のある女優として再スタートを切ったのだ。
『ぼくらの七日間戦争』に起用した菅原は、その変化をこう捉えている。
「スターは常に光を浴びる。その光が強ければ強いほど、濃い影が出るものです。人気がなくなれば手のひらを返され、周囲から人が去っていく。それをりえも体験したと思う。アメリカのショービジネスの世界には、『泳げ、さもなくば、沈む』という言葉がありますが、りえは本当に辛かった時も、必死に泳いでいたんだと思う。そういった経験を経て、表面的なものや話題性を追うのではなく、本質的にいいと思える仕事をしていきたいと考えたんじゃないでしょうか」
平成21(2009)年、野田作・演出の『パイパー』に出演中、妊娠と結婚が報じられた。35歳での結婚相手はハワイで知り合った一般人の日本人男性だった。
光子は孫娘の誕生は手放しで喜んだものの、この結婚には一貫して反対していたという。光子への反発から選んだ相手であったのかもしれない。光子とりえは以前のような「一卵性親子」ではなくなり、少し距離を置くようになっていた。
光子にも反対された、この結婚は長くは続かず、3年後には早くも不仲説が流れるようになり、長い離婚協議を経て、りえが親権を取って離婚が成立した。
その間も、蜷川、野田といった演出家に重用され、平成26(2014)年には7年ぶりに映画『紙の月』に主演。東京国際映画祭で最優秀女優賞を受賞する。
かつては彼女の婚約も、恋愛も、仕事もすべてが「話題」として消費された。歌や演技ではなく、彼女自身が商品だった。自分の存在自体が消費されていった。
だが、彼女はそうしたあり方に自ら決別をしたのである。別の見方をすれば、あまりにも突出し、存在そのものが特別だった「宮沢りえ」を放棄した、ともいえるだろう。
篠山紀信が言う。
「野田秀樹の舞台稽古でのりえがあまりにも素晴らしかったので楽屋に顔を出した。りえは放心状態でひとりボーッとしていた。僕が『すばらしかったよ』と興奮して告げても、彼女は喜ばず、『本当に?』とこちらを疑うように見つめた。僕は少し驚いて、『何言ってるんだ。最高だよ、りえ』と言い続けた。そしたら突然、駆け寄ってきて僕に抱きついたんだ。その時、思った。この子はこんなにも大きな不安を抱えながら、舞台に挑み続けているんだと」
宮沢家の血脈
りえと距離を保つようになった光子はパリと日本を行き来して、ひとり暮らしを楽しんでいた。
だが、体調を崩し診察を受け、余命を宣告される。日本で自宅療養をしながら、平成26年、肝腫瘍で旅立った。65歳の早すぎる死。それでも宮沢家の女性たちのなかでは最も長命であるという。光子の母も、姉のさつ子も短命だった。また、3人とも離婚を経験し苦労した。宮沢家の女性には、平穏には生きられない、あらぶる血が流れているのかもしれない。
母の死後、りえは舞台で共演したV6の森田剛と平成30(2018)年に再婚する。娘を連れて公園を散策し、気軽な店で食事をする姿がよく目撃されている。
光子は結婚の実態を知る先達として、りえに同じ轍は踏ませたくないと思っていたのだろうし、結婚すれば幸せになれるといった他力本願な生き方も嫌った。「りえにはカッコいい女になってもらいたいの」と周囲に語っていたという。
経済的にも精神的にも肉体的にも自立した自由な女、それが光子の理想とする女性像だったのだろう。光子が生きた昭和の時代、光子自身は理想を実現することはできなかった。その夢を娘の肉体を使って果たし、日本の男性社会に一矢、報いたかったのかもしれない。
昭和の末期に男女雇用機会均等法ができたものの、平成の経済停滞のなかで、十全には機能せず、むしろ保守化が進み、松明を掲げて女性たちを導く自由の女神は忌み、敬遠された。「宮沢りえ」は一度、居場所を失い、再び日本に戻ってからは注意深く世間と距離を取り、演技力という鎧で身を守っているようにも見える。
映画プロデューサーの奥山は、りえの平成における変化をこう語る。
「大人になり光子さんから離れる過程で、女優としてのスキルを磨く方向に向かった。その努力は立派だったと思う。でも、演技力という殻で身を覆い、固い女優になってしまった印象もある。
りえちゃんは自分の中にある昭和の情念のようなものを消して時代に合わせた。時代を的確に読んだけれど、少しそれが残念でもあるんだ。スターは多くの人の気持ちを引っ張っていくものだから、りえちゃんが相変わらず昭和っぽくて、松田優作が生きていたら、こういう平成じゃなかったかもしれない。
今の『宮沢りえ』は、本来の『宮沢りえ』を眠らせ、封印した上に成り立っている。意図的にりえちゃんが眠らせたんだと思う。でも、次の時代では、もう一度『宮沢りえ』で暴れて欲しい」
宮沢りえは昭和の残照がまだ色濃く残る中で、「宮沢りえ」というスターになった。
貴乃花との破局が伝えられた頃、昭和の名残も完全に消え、様々な問題点が噴出し、平成の不況へと突入していった。その「失われた10年」に、「宮沢りえ」もまた失われた。
女優として最も恵まれていただろう20代に、代表作を持てなかったのは彼女自身のせいなのか。それとも彼女を生かせなかった時代の責任なのか。
文字通り「平らかに成る」時代。すべてが平均化され停滞した。
ネット社会の到来もまた、社会の在りよう、人の意識を大きく変えた。憧れはすぐさま嫉妬に変わり、目立つものは標的とされ、スターであっても否応なく批判される。
平均化される世の中において、あまりにも突出していた彼女は傷つけられ、生き方を変えていった。時代の象徴、それがスターだ。
平成時代の光と影を、「宮沢りえ」の半生は浮き彫りにする。
(文中敬称略/「文藝春秋」2019年11月号)
ここから先は

文藝春秋digital
月刊誌『文藝春秋』の特集記事を中心に配信。月額900円。(「文藝春秋digital」は2023年5月末に終了します。今後は、新規登録なら「…

