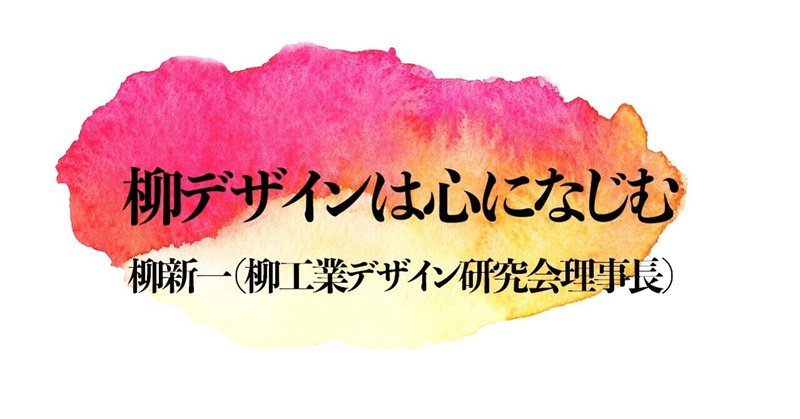
柳デザインは心になじむ 柳新一
文・柳新一(柳工業デザイン研究会理事長)
工業デザイナーだった父・柳宗理が亡くなって、この年末で10年になります。
父は生前、「プロダクトデザインは100年以上あるべき」と語っていました。その言葉どおり、ニューヨーク近代美術館の永久収蔵品であるバタフライスツールのみならず、柳デザインの多くが今も生き続けています。
鍋などキッチンウェア関連の近年の売上を見ると、右肩上がりではないものの、下がりもしません。メーカーがメンテナンスもしていて、100年どころか200年でも使える可能性があります。なので買い替えより、新しい使い手が年年増えているようです。これほど売上が安定した商品はそうないのではないでしょうか。
柳デザインのよさは、「誰のため、何のためのデザインか」という軸がぶれなかったことにあります。
高度成長期、父の関心は「作る」こと以上に「捨てられる」ことにありました。
きっかけは、東京・夢の島のゴミ埋め立てをめぐる大騒動だったと記憶しています。デザイナーが生み出したものが最後はゴミになる、大量生産、大量消費は資源を食いつぶし、環境を破壊する……とショックを受けていました。「デザイナーの仕事は罪だ」「これ以上、ものを作っちゃいけない」と言い始めました。
大学紛争で教授が学生たちの吊し上げにあったというニュースに接した時には、こう漏らしたものです。
「新一、若い人たちから1番吊し上げられるべきなのは、デザイナーだよな」
環境問題への悩みの深さを垣間見るようでした。
ここから先は
902字

noteで展開する「文藝春秋digital」は2023年5月末に終了します。同じ記事は、新サービス「文藝春秋 電子版」でお読みいただけます。新規登録なら「月あたり450円」から。詳しくはこちら→ https://bunshun.jp/bungeishunju
文藝春秋digital
¥900 / 月
月刊誌『文藝春秋』の特集記事を中心に配信。月額900円。(「文藝春秋digital」は2023年5月末に終了します。今後は、新規登録なら「…

