
文藝春秋が報じたがん患者の肉声 後藤正治
告知がタブーの時代もあった。ガンと人間との闘いを刻む痛切な記録/文・後藤正治(ノンフィクション作家)
難敵に対するさまざまな武器
深代惇郎(ふかしろじゅんろう)氏は「朝日新聞」の朝刊コラム「天声人語」の書き手であり、名文家として知られたが、執筆期間は2年9カ月に過ぎなかった。血液のガン、急性骨髄性白血病で急逝する。46歳の若さだった。
半世紀近く前のこと。いまならHLA(白血球の型)が合う他者から提供される骨髄の移植が模索されようが、当時は未知の分野だった。
白血病=不治のガンとされた時代であり、妻の義子氏は主治医のアドバイスに従い、タチ悪い緑濃菌が入り込んで……という偽りで押し通した。深代が最後まで、そのことを信じていたかどうかは不明であるが、短い闘病ののち、彼岸へと去っていく。
この半世紀の間に、ガン治療のありようは随分と変わった。告知は是か非か――が盛んに議論された時代もあったが、告知それ自体はもうあたりまえのこととなっている。
腫瘍部を切って除去する、抗ガン剤を投与する、放射線を照射する――主要なガン治療の手段であるが、腫瘍の場所によって、進行度によって、効果はグレーだ。そのことはいまも変わらないが、精度が増し、新しい治療法が登場し、われわれは難敵に対してさまざまな武器を保持するようになった。正規軍もあればゲリラ部隊もある。本誌での記事を読み返しつつ、ガンとのたたかいの一端を記してみたい。
1975年6月号 ガン病棟の九十九日 児玉隆也
1974年10月号 がんセンター総長の“戦死” 塚本哲也
1981年5月号 乳ガンなんかに敗けられない 千葉敦子
1999年5月号 妻と私 江藤淳
2001年5月号 精神科医がガンになって 頼藤和寛
2008年4月号〜7月号 僕はがんを手術した 立花隆
2009年2月号 がん残日録 筑紫哲也
2003年11月号 女ひとり、四十歳でがんになる 岸本葉子
2021年9月号 「池江璃花子は病室で笑った」 吉田正昭
「ガン」は禁句
本誌に、立花隆氏の「田中角栄研究 その金脈と人脈」および児玉隆也氏の「淋しき越山会の女王」が掲載されたのは1974(昭和49)年11月号であるが、田中退陣の引き金となった。間を置かず、児玉の「ガン病棟の九十九日」(1975年6月号)が掲載されたのも衝撃だった。

児玉隆也氏 ©文藝春秋
がんセンター(現・国立がん研究センター)での肺ガンをめぐる闘病記であるが、37歳という若さである。まさか……という思いに駆られた。
このレポート時と現在との際立った相違は、病院側も患者もほとんど「ガン」を禁句として避け続けたことである。
《奇妙なことだが、この日病院で交した会話の中に、癌という言葉は、ほとんど省略されていた。医師は「七〇パーセント(癌の)疑いがある」。私は「まだ(癌だと)決まったわけじゃない」。妻は「あの……やっぱりそうなのでしょうか」といったが、癌の本山に来て癌を禁句にする神経は、私だけではなかったようだ。後に「癌患者」となって病棟に入ると、仲間たちは「この病気」と呼んでいた》
以下の、看護婦との会話なども象徴的である。
《もちろん彼女はいきなりこう訊くわけではなく、最初は例によって病歴だった。それから食べものの好き嫌い。つまりは、無難な質問が、じわじわと癌に近づいてくる。
煙草は一日に何本吸っていましたか?
それからさっきの質問になり、最後の質問が、このまだ娘っぽい看護婦の口から発せられるには、重大すぎた。彼女はこう言ったのだ。「信仰はおもちですか」
その瞬間、私の中のあらゆる神経の中から、猜疑心だけが、ものすごい勢いで噴出した。そして、私の体中の神経が漏電し、医師や看護婦の一言に確実にショートし始めた。
私は「いえ、別に。信仰はありません」と答えながら〈そうか、死ぬ時の用意か〉と思った》
このあたりの記述、当時においては、ガン=死の宣告であったことがよく伝わってくる。
実際、連日、がんセンターでも患者はばたばたと亡くなっていて、児玉はこんな一句も残している。
【棺一つ 行かぬ日はなし 癌病棟の冬】
なお、児玉は本稿執筆から間もない、1975年、38歳で亡くなっている。
現役がんセンター総長の死
1970年代、ガンにかかわる痛切なレポートとなったのは「がんセンター総長の“戦死”」(1974年10月号)であろう。総長・塚本憲甫(けんぽ)氏の子息、哲也氏(当時・毎日新聞外信部副部長)が寄せた一文であるが、読者には“総長にしてなおそうなのか……”という思いがよぎったものだった。
総長は、放射線によるガン治療にたずさわってきた医学者であったが、被曝線量の積み重ねのせいか、常人に比較して白血球が半分しかなく、すなわちガンに対する抵抗力が弱く、それゆえ“戦死”という表題が使われている。
前年の12月、塚本は胃ガンの手術を受けている。この手術自体は成功したが、哲也への専門医たちの説明は、「胃壁の中の血管にはがん細胞が無数に巣食っており、すでに肝臓には8センチ四方のこぶし大の大きながんが転移しており、肺にも2カ所転移している」「1年以内に80%が亡くなる」というものだった。
病状について、哲也たち家族は父に伝えることをしなかったが、「なにしろ、父は老練のがんの医者である。ポーカーフェイスではとても太刀打ちできる自信はなかった」とある。
家族は隠せたと思い込んでいたが、父はすべてお見通しのようだった。この時期、塚本は、日経の「私の履歴書」の連載を執筆していたが、最終回の原文ではこう記している。
《スペインから帰って、胃がんを発見し、……がんセンターの専門家チームで、時を移さず手術をしてもらった。おかげで私はふたたび健康を取り戻し、いまは元気に通勤している。しかし、私は永年放射線を浴びつづけ、がんの転移に対する抵抗力がない。したがって、第二、第三のがんができる可能性は多いし、もはやすでに転移しているかもしれない》
「第二、第三のがん」云々のくだり、家族たちの「縁起が悪い」という意見を入れて、不本意ながら文を削ったとある。
ガンにおけるプロ中のプロ医師においてなお、このような一幕があったという記述、往時のガンを取り巻く風潮の一端がうかがえる。
なお塚本は、病床で洗礼を受けて亡くなっている。
千葉敦子氏の「乳ガンなんかに敗けられない」(1981年5月号)は、日米両国でジャーナリズム活動を展開してきた千葉の奮闘記である。

千葉敦子氏 ©文藝春秋
40代に入っての、発病―手術―再起の日々を赤裸々に綴っているのは、「この経験をまとめて記事にするつもりだったから」とある。病を見詰め、自身のプライバシーも明かしつつ、内面を仔細に記す筆致は小気味いい。アメリカ流ジャーナリストの精神のなせることでもあるのだろう。
左の乳房を失った意味についてこう記している。
《ストリッパーやヌード・ダンサーなら仕事を失うから深刻だろうが、そうでない女が乳房を喪っただけで生きる気力を喪失してしまうというのはどういうことだろう。いったいその女の価値観、人生観はどうなっているのか。そんなふうに思わせる夫や恋人は、いったい女に何を求めているのだろう。たとえば、今もなおこの地球上で、おびただしい数の子どもたちが餓死している。その事実に思いを馳せただけでも、たべるものが充分にある環境で、乳房一つ喪ったくらいが何だというのか》
そして、ガンを患った意味について、こんな考察を下している。
《私が今回の経験から得たものは測りきれない。その一々をここに記すのはひかえるが、基本的には、生死を考えるとき、瑣末な問題はどうでもよくなるという認識である。たとえば、つまらぬことに時間を費したり、つまらぬ仕事を引き受けてはいられないと思う。
私にとって幸福は金や名誉とは無関係であり、本当に好きな仕事を持ち、人を愛し人に愛されることにつきるということも確認した。(中略)
そして……失ったものは、たった乳房一つだけだったのである》
別段、ガンに特化されることではあるまいが、病は人に、何が本当に大切かということを教えてくれる契機となりうる。その意味でガンは、マイナス面だけでなく、思考の深化を促すものを含んでいる。
ガンと共生しつつより充実して生きる――そんな生き方を続けていた千葉であるが、1987年、46歳で亡くなっている。
「告知は、いたしません」
評論家・江藤淳氏の「妻と私――四十一年間連れ添った愛妻への鎮魂記」(1999年5月号)は、末期ガンの妻を支え、見送った夫の手記である。
慶子夫人の疾患は、肺および脳に複数の腫瘍が認められる末期的なガンだった。「告知」にかかわって、こんな一節が見られる。
《突然の死(サドン・デス)……救急車で運ばれて行く道すがら、絶命する家内の姿が脳裡に浮んだ。
「早くて五月、遅くても八月か……」
私は誰にいうともなく、つぶやいた。
「告知は、どうされますか?」
と、Y院長が質した。
「告知は、いたしません」
私は言下に答えた。その瞬間に、重苦しい沈黙が医師たちのあいだに流れた》
告知をしないと言い切ったのは、もはや有効な治療手段がない中、告知はそのまま死の宣告になるからであった。
夫人が亡くなるのは1998年11月。告別式の前後、江藤自身が急性前立腺炎と敗血症で倒れ、当時の模様は凄絶である。ようやく退院にこぎつけたところで筆を置いているが、夫人の後を追うように、翌年7月、江藤は自裁する。
子供はなかった。自裁の後、姪(慶子の姉の子)の府川紀子(ふかわのりこ)は「可哀相な、おじさま」(1999年9月号)で、その前後の事情に触れつつ、「いまにして思えば、おじさまが自らの命を断ったのは考えぬかれた末のことではないでしょうか。6月10日の脳梗塞のあとから。あるいは、もっと、もっと前から」と記しているが、夫人と折り重なるように逝ったという気配が漂う。
“名文”が残された。
《心身の不自由は進み、病苦は堪え難し。去る六月十日、脳梗塞の発作に遭いし以来の江藤淳は形骸に過ぎず。自ら処決して形骸を断ずる所以なり。乞う、諸君よ、これを諒とせられよ。
平成十一年七月二十一日
江藤淳》
読者ということでいえば、私は江藤の文芸評論の、ごく淡い一読者に過ぎなかったが、この一文は残った。諒――とする以外の、どんな感想があるのか。いまも同じ思いが湧くのである。
死期迫る日々をユーモラスに
頼藤和寛(よりふじかずひろ)氏の「手記 精神科医がガンになって」(2001年5月号)は、その後『わたし、ガンです ある精神科医の耐病記』(文春新書)として刊行された。直腸ガンに侵され、手術後、とりあえず退院はできたものの、死期迫る50代の日々を見詰めた実存的な書である。
頼藤は大阪生まれ。阪大出身で、外科医を経て精神科医へ転身している。重いテーマを扱いつつ、本書を魅力ある読みものとしているのは、精神科医としての深みある視野と、大阪人らしい、諧謔的ユーモアが散見されることだろう。
《街を歩いても、すれちがう人々はたいていわたしより長く此の世にとどまるだろう人々である。これを思うと一種の疎外感を禁じ得ない。(中略)余命で負けない自信のある相手といえば鮮魚コーナーでヒゲや脚を動かしている活けエビ活けカニぐらいのもので、さすがにわたしのほうは今夜中に焼かれたり蒸されたりはしないだろうと、ようやく優越感に浸れるのである》
病院というものをこう記している箇所もある。
《そんなところに甘い期待を抱かず、用が済めばさっさと縁を切るのが賢明だろう。そうでなくても、警察署、裁判所、税務署と並んで一生行かなくて済むに越したことないのが病院・診療所なのだ》
いやその通り――と私などは思ってしまう。
本書は、抗ガン剤や放射線治療の功罪、また代替医療の効用についても触れているが、記述は冷静で客観的である。
いわゆる食事療法も取り入れてはいるが「自宅では家内の監督下」にあり、「内心ではそれほど効果に期待しているわけではない」。「今生(こんじょう)で味わえる食事の回数も限られているだろうから、好きなものばかりを心ゆくまで食べて死にたい」と思うが、「祈るような気持ちで作ってくれている延命メニューを徒(あだ)や疎(おろそ)かにもできないではないか」とも書いている。
往時と比較すれば、患者負担の少ない、非侵襲的な検査手段も進んできた。代替医療のメニューもバラエティに富んでいるが、個別の効用報告はあれ、全体として明瞭なエビデンスが示されているものは少ない。諧謔味を利かせた、こんな記述も見られる。
《もとより、現代医学のアンチテーゼである代替医療や伝統的な養生法を勧めて回る信心深さの持ち合わせもない。要するに、倫理コードも業界も鰯の頭も斟酌(しんしゃく)せず、見たこと聞いたこと考えたことを遠慮なく書き連ねていきたい。近々死ぬことも勘定に入れている人間に怖いものなどないのだ。言いたいことを言ってやる。くやしかったら「あの世」まで追いかけてこい》
「認識の鬼」という言葉も見られるが、身辺に立ち込める死の気配を知覚しつつ、ガンのもたらすものを見詰めている。本書に通底する視座は、ラテン語の箴言「メメント・モリ」(汝、死すべきを銘記せよ)である。なお、本書刊行後間もない2001年、氏は53歳で亡くなっている。
ガンと生命は本質的に不可分
大いなる知の探究者、立花隆氏の訃報が伝えられたのは2021年初夏であるが、これ以前、「同時進行ドキュメント 僕はがんを手術した」(2008年4月号〜7月号)の連載を目にしていた。
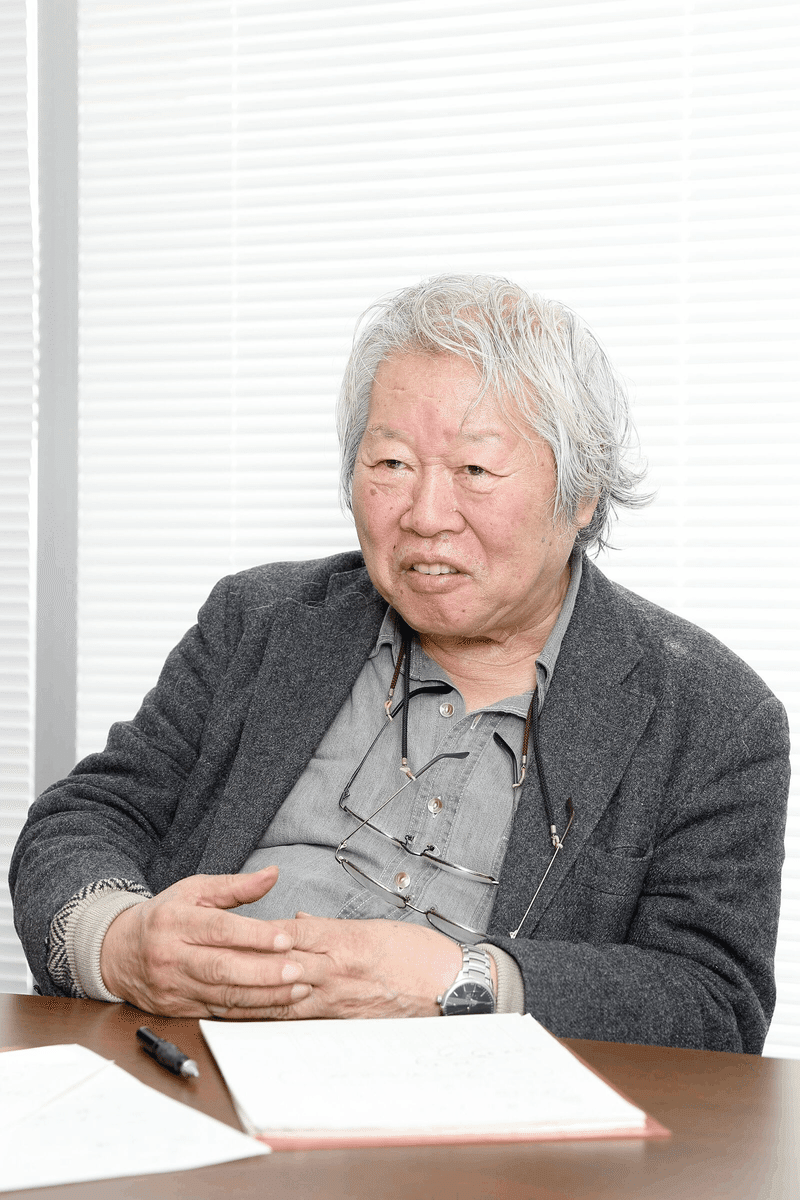
立花隆氏 ©文藝春秋
膀胱ガンの発生、東大病院泌尿器科での診断、手術……を記したものであるが、氏らしい、精緻なる描写には圧倒される。
ここから先は

文藝春秋digital
月刊誌『文藝春秋』の特集記事を中心に配信。月額900円。(「文藝春秋digital」は2023年5月末に終了します。今後は、新規登録なら「…

