
もう一つの“東京1964”「56年前のパラリンピック」卓球ダブルスで銅メダルを獲得した、ある女性の物語
文・稲泉連(ノンフィクション作家)
プロフィール/1979年生まれ。早稲田大学第二文学部卒。2005年、『ぼくもいくさに征くのだけれど―竹内浩三の詩と死―』で大宅壮一ノンフィクション賞を受賞。主な著書に『復興の書店』『豊田章男が愛したテストドライバー』『「本をつくる」という仕事』『宇宙から帰ってきた日本人』がある。
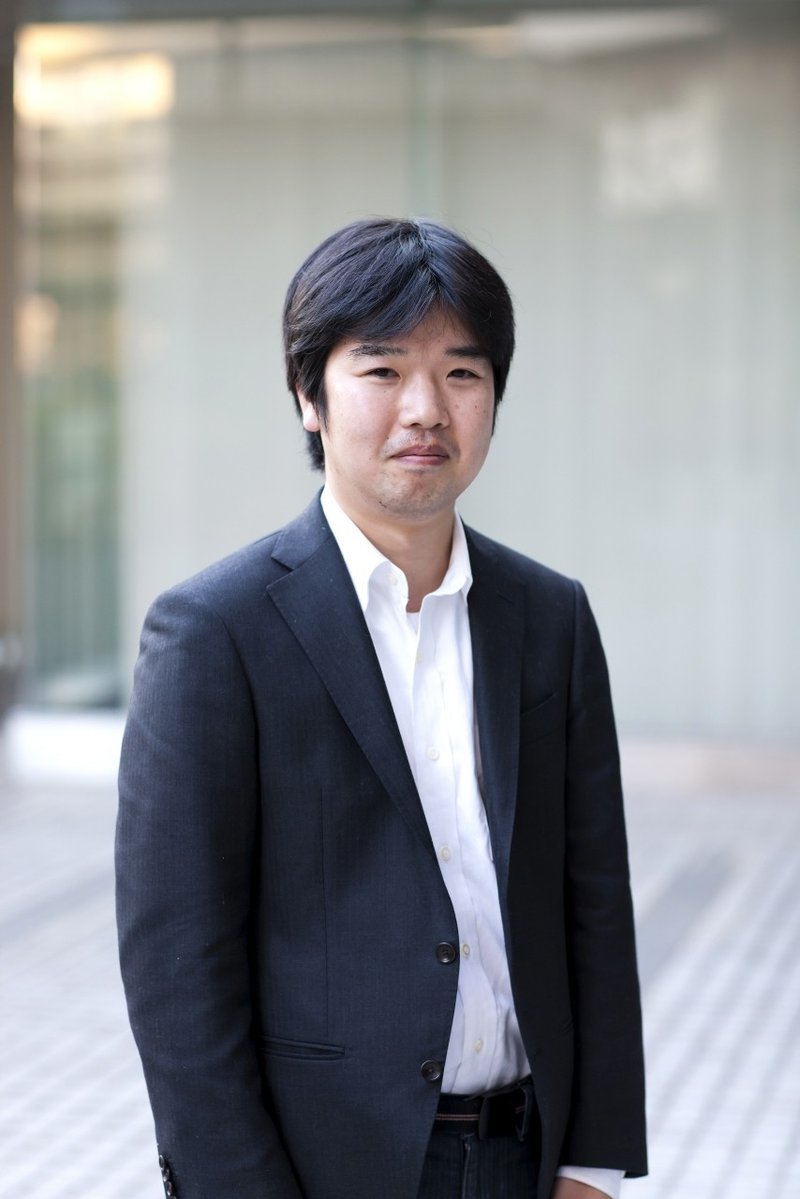
現在のパラリンピックの源流となる大会
今から56年前の1964年のことだ。10月に行なわれた東京オリンピックが閉幕した2週間後、選手村のあった代々木の「織田フィールド」という練習用競技場で、障害者の国際スポーツ大会が開かれた。大会の発祥であるイギリスの病院の名を取って「第13回国際ストーク・マンデビル競技大会」とも呼ばれたその大会は、「第2回パラリンピック」として今では知られている。
日本で初めての障害者の国際スポーツ大会であった「1964年のパラリンピック」は当時、国際大会と国内大会に分けて開催された。現在のパラリンピックの源流でもあるその国際大会は、戦争や事故で脊髄損傷となった車椅子の人を対象としていた。参加者は世界22か国から369人、そのうち日本人選手は53人が出場した。日本代表のほとんどが国立箱根療養所や国立別府病院など、施設や病院の〝入所者〟や〝患者〟であった。
私は今年の3月、この大会に関係した様々な人々を取材し、『アナザー1964 パラリンピック序章』という本を書いた。
ここでは同書の中から、笹原千代乃さんという一人の女性選手のインタビューの模様を紹介したい。53人の日本選手のうち女性の出場者は2人だったが、彼女はその1人として当時の大会を体験し、卓球のダブルスでメダルを獲得している。
彼女を私に紹介してくれたのは、オーダーメイドの車椅子を作っていた「ウイールチェア」の元代表の後藤章夫さんである。当時の日本には競技用の車椅子はもちろん、現在普及しているような一般的な車椅子もほとんど使用されていなかった。笹原さんのいた箱根療養所でも、「箱根型」と呼ばれる三輪の木製の車椅子が使用されていた。それは第一次世界大戦の際に、負傷した兵士を運ぶために作られたものだった。
そんななか、後藤さんは欧米型の新しい車椅子を開発するため、箱根療養所に何度も足を運ぶなかで笹原さんに出会ったという。
彼女のインタビューを行ったのは、2018年10月のことだった。後藤さんに教えてもらった御殿場の近くの住所を頼りに車を走らせると、車一台がぎりぎり通れる道を登った小高い丘の上に、80歳を超えて一人で暮らす彼女の平屋の一軒家はあった――。
「あの経験がなければ結婚もしなかった」
「パラリンピックに出た後、わたしはあちこち転々としたけれど、昭和44年にこの家を建てたの。療養所で出会って結婚を約束した人に1年待ってもらってねェ。小田原の大工さんにお願いしたのですが、彼も車椅子用の家を建てるのは初めてだと言っていました。我が家にあるスロープはそのときのままなのよ」
車椅子に座る彼女は猫背の小柄な女性で、年のせいか耳が少し遠くなっていたが、一つひとつの仕草や表情に愛嬌を感じさせる女性だった。神奈川県におけるバリアフリー住宅の「最初の一軒」であったかもしれないという自宅で、彼女は車椅子を自分の体の一部のように今も扱いながら、私にお茶を運んで淹れてくれた。
「わたしたちの家が建ってから、たくさんの人たちが見学に来て、神奈川県でも障害者住宅がいっぱいできるようになったの。障害者同士で結婚する人たちも増えましたしねェ。だから、たくさんの人たちがこの家に集まって、わたしはまるで飯場の女将さんみたいになった。料理も練習してとても上手になって――。ええ、あの大工さんはこの家を建ててから、何十軒とこういう家を建てたのじゃなかったかしら。
わたしはパラリンピックには卓球で出たのだけれど、あれ以来、卓球なんてしたことがありません。でも、こうして外の世界に出てこられたのは、パラリンピックが第一歩だったと思う。夫はもう亡くなってしまったけれど、あの経験がなければ結婚もしなかったと思うから」
箱根療養所からパラリンピックに出場した彼女は、本人が語るように卓球のシングルスとダブルスに出場した。ダブルスを組んだのは開会式で旗手を務めた小笠原文子さんで、そのときが初対面であったという。
笹原さんは結婚前の姓を井上と言い、パラリンピック開催の半年前に箱根療養所に入所した。脊髄に怪我を負ったのはその前年のことで、それまでは東京の丸の内にある法律事務所の事務職員として働いていたと言う。
当時を物語る記憶は今も鮮明で、私は質問を重ねながら、彼女の語る「もう一つの1964年」をめぐる話に引き込まれていった――。

1964年11月8日、青野繁夫氏の選手宣誓によって幕を開けた。ちなみに青野氏は傷痍軍人。提供:青野行雄氏
ある雨の日、彼女の人生は暗転した
「わたしね、山梨県の石和町の生まれなの。7人きょうだいの下から2番目。父は果樹園をしていて、母は温泉旅館をしていたのだけれど、子供の頃はまだ町に温泉は出ていなくてね。あるとき、田んぼを掘ったら湧いてきたというので、大騒ぎになったのよ。そのお湯の温度はとても高かったけれど、川に流れてちょうどいい具合になっていてねえ。それで、友達とみんなで水着になって浸かりにいったのを覚えています。母はその温泉の権利を買って旅館をはじめたのね」
――スポーツは得意だったのですか?
「そうですねェ。わたし、そう言えば子供の頃からスポーツは大好きだったわね。ドッヂボールも得意だったし、中高時代はバレーボールをしていたの。高校のときはボール拾いばかりだったけれど。勉強をあまりしなかったから、本当は山梨大学に行きたかったんだけれど、受験はしませんでした。それで東京に就職で出てくることになったんです」
――東京ではどういうお仕事をされていたのでしょうか?
「でも、昭和30年頃の話でしょ? 就職難でねえ。たまたま優秀な兄が司法試験の勉強をしていて、東京の法律事務所に伝手があったの。それで、19歳のときに第二東京弁護士会というところで働き始めたのね。兄が勉強をしながら、そこで書生をしていたから。仕事はタイピストでした。ただ、もちろんタイプなんてしたことないから、桜木町のYMCAで3か月間、タイプの練習をしてから働き始めたの。思えば、すごい事務所だったわねェ。だって、大勢の弁護士さんがいたんですから。その人たちが謄写版でいろんな書類を印刷するのを手伝うんだけれど、1枚の書類を打つのに容易じゃなく時間がかかるので、徹夜仕事はしょっちゅうでした。きっと、若かったから出来たのね」
笹原さんが脊髄損傷の怪我をしたのは、そうして東京の法律事務所で働き始めて数年が経ち、仕事にも慣れた頃のことだった。給料日の雨の日、事務所に向かう途中の東京駅の階段で、前から駆け下りてきた人とぶつかった。ヒールの高い靴を履いていた彼女は足を踏み外し、階段を転げ落ちてしまったという。
「気を失って、あとのことは覚えていません。気が付いたら近くの病院にいて、それから医科歯科大学を紹介されて移ったみたい。とにかく、気が付いたときはベッドの上でした」
医科歯科大学病院に入院中、彼女は医師から脊髄に深刻な怪我を負っていることを伝えられた。
数か月間続いた入院生活はつらいものだった。怪我をしたばかりの彼女は、自分で車椅子に乗ることができなかったし、そうしようという気力も湧かなかった。当時、病院には患者を運ぶための医療用の車椅子があった。寝かせた状態で患者を乗せた後、背を起こすことのできるストレッチャーのようなタイプのもので、本郷にある製作所で作られていたという。彼女は看護婦に頼んでその車椅子に乗せてもらうと、よく病院の屋上に連れて行って欲しいと言った。
「屋上に行って外の景色を見ながら、ここから飛び降りたらどうなるかな、なんて思ったり……。そんなつらいことばかり考えていましたよね」
今の彼女は昔話を物語るように、少し笑みさえ浮かべながらか細い声で言った。
「でも、塀があって、とてもそれを乗り越えられないから、自分で覚悟して、『ああ、これはやっぱりまだ生きろということなんだな』って思っていたんです」
彼女の家族は脊髄損傷の患者を受け入れる施設として、箱根などに療養所があることは入院時の主治医から聞いていた。だが、担当の医師からも「ここにこれ以上いても仕方がない。どうしても専門の病院に行かなければならないのだが……」と言われていたものの、実際に藁にも縋る思いで箱根療養所に連絡をしてみると、80人以上が入所待ちの状態だった告げられた。さらに他の脊髄損傷を診察できる整形外科や療養所にも連絡を取ったが、どこにも空きは見つからなかった。
そんななか幸運だったのは、親戚の一人が看護婦をしており、箱根療養所の医師に伝手を頼って連絡が取れたことだ。
早速、紹介してもらうと、しばらくして療養所の医師が所沢の家までわざわざやってきた。そこで彼女は、全く想像もしていなかった提案を彼から受けることになる。
「今度、東京オリンピックのあとにパラリンピックという大会がある。もしその大会に出てもらえるのなら、療養所に入ることができるが、どうだろうか?」
1964年の春の出来事だった。

大会開催時、美智子妃は積極的に選手たちと交流した。提供:浜本恵子氏
「パラリンピックには行きたくなかったの」
――パラリンピックの話を医師から聞いたとき、どのように思いましたか?
「先生にそう言われたとき、わたしはもちろんパラリンピックなんて聞いたこともありませんでした。それで、大会には50人くらいの日本人が出る予定になっているけれど、女性の出場者が少ないのだと先生は仰るんです。旗手を務めた小笠原さんはもう亡くなっちゃったけれど、当時、彼女は横浜の方の病院にいて、ばんばん車椅子を使っていたそうです。
でも、他に女性選手がいないと、卓球のダブルスにも出られないでしょ。だから、『もう一人くらい女性の出場者が欲しい。そもそも日本で海外の人たちを迎える大会なのに、女性がいないのはおかしいという話になっている』ってねェ。
要するに、わたしがパラリンピックに出られるような患者だったら、優先的に箱根に入れてあげる。もしダメだった帰ってもらうというわけです。所沢の家から入所するための支度をぜんぶ、用意して箱根に行ったのだけれど、『ダメだったら持って帰ってもらうからね』と念を押されたんですから」
――出場するつもりがないのであれば療養所には入れない、と。
「わたしはね、あんまりパラリンピックみたいなところには行きたくなかったのよ、本当は。だって、怪我をしたことだってまだ受け入れられていなかったのに。そんなときに、国際大会と言ったってねえ……。人前に出るのが嫌で嫌で、そんな恥ずかしいことしたくない、っていう気持ちでしたよ。でも、わたしには選択肢はなかったの。だって、家にいてもどうにもならないし、療養所は満杯でどこも空いていないんですから。パラリンピックに出ないと箱根にはいられないのだから、みんなからも『どうしても出るように』って言われて……。だから、わたしはしょうがなくパラリンピックに出たんです」

パラリンピックの予算、約9000万円の大半は民間からの寄付で賄われた。実施本部には全国から折り鶴も送られた。出典:『PARALYMPIC TOKYO 1964』
マンツーマンで練習
箱根療養所は現在の箱根登山鉄道の「風祭」駅の近くにある。山にへばりつくようにして病棟が建つ坂の多い施設で、戦前には「傷兵院」と呼ばれていた時期もある。その名の通り、戦争でけがをした傷痍軍人の暮らす療養所として始まったもので、当時の入所者には日露戦争時の戦傷者もいた。
療養所に始めてきたとき、彼女の目を引いたのは15メートルほどのプールがあったことだ。地面を掘ってビニールを敷いたプールで、パラリンピックのために急ごしらえで作った練習用のものだったという。
「そこにまずは連れて行かれて、『泳いでみなさい』と言われたの。わたし、山梨の生まれで、子供の頃は川で泳いでいたでしょ。だから、簡単に泳げると思っていたけれど、あれは流されているだけだったのね。結局、腕と手をばたばたするばかりで、ちっとも泳げやしない。水もがぶがぶ飲んじゃった」
すると、次に医師から勧められたのが卓球だった。何度か練習をすると「ひとまず合格」ということになり、医師から「パラリンピックまであと半年ある。コーチをつけるからマンツーマンで練習をしてみなさい」と言われた。
「そうして箱根で暮らし始めたときのことは、忘れもしません。最初は部屋が空いていなくて、レントゲン室の隣にあった天井の高い部屋に入れてもらってねェ。こう言っては申し訳ないけれど、そのときは『なんだか牢屋みたいな場所だなァ』って思った。でもね、そんなふうに最初は暗い気持ちだった箱根の生活が、わたしはだんだんと好きになっていったの」
――療養所での生活はどのようなものだったのでしょうか?
「たとえば、はじめに入った隣の部屋にYさんという女性がいた。彼女は療養所の傷痍軍人の方と結婚していて、隣から新入りのわたしのことを『頑張って』って応援してくれたの。彼女と知り合ったときは、本当に驚いたわねェ。彼女は『あなたも結婚しなきゃダメよ』といつも言っていたのけれど、わたし、脊損なんて結婚なんて夢のまた夢、そんなことぜんぜん考えたこともなかったから。
そのレントゲン室の隣から、今度は女性の4人部屋の普通の部屋に引っ越したの。怪我を受け入れる気持ちにはなれなかったわたしは、ここはイヤだと最初は母に言っていましたけれど、ところがそうやって相部屋の人たちと話すと、みんなとても明るいのが意外でした。
『怪我をしてから何年くらい経ったの?』
そう聞いたら、同室のAさんは『13年』って言う。
あの頃の脊損といったら、3、4年かそこら生きられればいいと言われていた。わたしはそれどころが、明日死んでもいいっていうくらいの気持ちだったのに、彼女は13年と言う。思わず聞き返しました。『13年も生きるの?』って。そうしたら、Aさんは笑ってこう続けたのよ。
『なに言ってるの! 傷痍軍人の人たちのなかには、もっと長い人がいくらでもいるわよ』
彼女たちは、いろんなことを助けてくれました。布おむつも持って来てくれたし、トイレの練習も手伝ってくれた。それから、男の人たちも車椅子に乗る練習を手伝ってくれました。
だから、わたしの箱根の第一印象は『人が明るい』ということでした。でも、どうして明るいんだろう? しばらくすると、その理由が分かるような気がしてきました。
例えばね、病院のご飯が美味しくなければ、それは食べないでラーメンを作ったり、鍋でご飯を炊いたりしていてねェ。風祭の町にお魚屋さんや八百屋さん、米やさんも床屋さんもあったし、必要なものはだいたいそろっていて、電話をすればすぐに持って来てくれる。病室には御用聞きが来て、薬局の人も『薬はいかがですか』なんて言って入ってくるんだから。野菜屋さんがあったり、床屋さんもあったし、みんな町にそろっていたの。療養所にはそんなふうに療養所の生活がある。それに慣れてしまってからは、何だか楽しくもなってきて、療養所を離れるのが今度はイヤになってきた心持ち。死んでしまいたいと思っていたのが嘘みたいでしょ」
――1964年のパラリンピックでは、同じ箱根療養所の傷痍軍人だった青野繁夫さんが選手宣誓をしています。傷痍軍人の人たちは一般病棟ではなく、西病棟という離れで生活していたそうですね。
「傷痍軍人の人たちとも、もちろん仲良くさせてもらいました。青野さんのことは特に尊敬していましたね。『ちよちゃん』と呼んでくれていた気がするなァ。これはパラリンピックの後の話だけれど、その西病棟にはご飯に呼ばれたときも坂を登っていくけれど、さらにその上にアーチュリーやバスケットの練習ができるグラウンドがあったんです。そこに友達と一緒に行って――その頃は車椅子から降りたり上がったり自分でできるようになっていたから――車椅子から降りて寝っ転がって、青空を見ながら将来の夢を語り合ったりもしたのよ。そのときのわたしの将来の夢が、『家を建てる』ということでした」
――パラリンピックに向けての練習はどのようなものでしたか。
「箱根はね、そんなわけでとにかく坂ばっかりなんです。車椅子のわたしたちにとっては、半端じゃない坂なんだから。それを毎日、上り下りしたから、うんと力が付いた。先生に言われて始めた卓球も、意外と筋がよかったのね。最初はピンポンだったけれど、練習を続けるうちに男の人とも対等に打てるようになった。そうして、パラリンピックまでのわたしの6か月間は過ぎていったのね」
では、彼女にとって東京でのパラリンピックの体験は、どのようなものだったのだろう。

アーチェリーの競技模様。出典:『PARALYMPIC TOKYO 1964』
なぜ外国人選手は大会を楽しめるのか
箱根療養所から出場する選手たちは、11月8日の開会式の2日前に東京へ向かった。
療養所の入所者たちの多くは、東京どころか施設のある「風祭」を出るのもほとんど初めてのことだったと思われる。
用意されたイギリス製の車椅子が積まれたバスに、職員に抱えられて乗せられると、国道一号線の風景が車窓に流れていった。緊張感や「見世物にされるのではないか」という不安感がない交ぜになり、目的地が近づくに連れて彼女の気分はむしろ沈み込んでいったようだ。
「だから、私はパラリンピックがどんな大会だったのか、あんまり覚えていないの」
と、彼女は笑った。
「だって、もともと乗り気じゃないところに、女性が2人しかいないから何しろ目立ってねェ。映画を撮っている人もいるし、テレビもいるし、生まれ故郷の山梨からも取材が来るし……。行くところ行くところにカメラがあるでしょ。だから、車を押してもらっている間も、わたしはずっと下を向いていたの」
彼女は会場に到着してからずっと取材陣から逃げ回ってばかりいたが、開会式で青野の宣誓を間近に見た後、卓球の試合では小笠原と組んだダブルスで3位に入る好成績を見せた。
そうした試合を終えると、彼女にもようやく心の余裕が少しずつ生まれてきた。車椅子バスケットを会場に見に行った際は、外国人選手の車椅子の捌き方の巧みさに驚いた。そして、そのなかで彼女がとりわけ興味を持ったのが、周囲を行き来する女性外国人選手たちの姿だった。彼女たちのなかに、足がとても綺麗な選手が多いことに気づいたからだ。

選手村内の食堂・富士にて。日本人選手からみれば、外国人選手の表情は明るかったという。出典:『PARALYMPIC TOKYO 1964』
日本人選手団は自分と小笠原も男性選手と同じズボンをはいていたが、海外選手の中にはスカートを身につけている人も多かった。そこに見える足が太くて美しかったと彼女は言う。それがどうしても気になって、海外選手たちの通訳を担当していた「語学奉仕団」の1人に聞いてもらうと、ストッキングに綿を入れて足を綺麗に見せているとのことだった。
この話を聞いて、「ああ、そうなのか」と笹原さんは彼女たちに俄然興味が湧いてきたと話す。そこで、彼女は閉会式の際、語学奉仕団のメンバーに頼んで、オランダなどの選手数名に通訳を交えて話を聞いた。なぜ外国人の選手たちは、この大会をあれほど楽しむことができるのか。
「わたしなんて日本人選手のなかで、いちばんうつむいていたから、本当に不思議でねぇ。そうしたら、みんな結婚していて、子供もいて、家にはプールがあって、自動車を運転していて……と次々に言ったの。その頃、わたしは死ぬことばかりといったら大げさだけれど、そんなことしか考えていなかったから、本当に驚いたんです」

現在は、人気スポーツとなった車椅子バスケットボールだが、当時の日本代表は一勝もできず。提供:浜本恵子
閉会式で「気づき」を得た
パラリンピックの第一部の閉会式は10月12日、午後五時から国立総合体育館の別館(第三会場)で行なわれた。空模様は曇りがちで小雨が降っていたが、会場には開会式同様に3000人の観客が訪れていた。参加22カ国369人の選手たちが整列し、天井からの照明が車椅子の車輪に反射してきらきらと光っていた。
午後5時ちょうどのファンファーレとともに始まった閉会式では、女学生120人の「パラリンピック賛歌」が合唱で披露された後、真っ白なターバン風の帽子とコート姿の美智子妃によるトロフィーの授与が行なわれた。そのうちの一人であるフランスの男子フェンシング・サーベルの選手は妃殿下から「銀の剣」を受け取り、騎士道に則って剣を縦にして敬礼するシーンは、閉会式を象徴するものの一つとなった。
この閉会式の最も感動的な一幕は、グッドマンや葛西の挨拶が終わり、君が代が吹奏されるなかで掲げられていた日の丸やSMG旗が降納された後に起こった。次期開催国の名がアナウンスされ、今度は「蛍の光」が会場に流されての選手退場となった。だが、彼らはなかなか会場から去ることなく、体育館の中心に輪となって集まり、車椅子から伸びあがるようにして握手を交わした。
手を叩き合い、帽子を投げ、肩を抱き合う彼らの姿に対して、会場からは自ずと割れるような拍手が巻き起こった。会場には選手たちの声が反響し、次第に彼らは選手同士だけではなく、会場を訪れた観客たちとも握手などをして交歓が続いたのだった。
その輪のなかにいた笹原は、何か言いようのない気持ちが胸の奥から湧き上がってくるのを感じていた。選手村に来たとき、ずっと下を向いていた気持ちはいつの間にか消えていた。
ふと「待てよ」と彼女は思った。
「もし、あのオランダの女性選手たちのようにこの社会で生きていけるのであれば、自分も挑戦してもいいのかな」
閉会式のとき、彼女は「心のなかで確かに何かを感じていたのね」と言う。
「わたしだってオシャレをしたり、結婚したりできるかもしれないじゃないか、って。もう一度だけ、自分の力を試してみよう、って」
祭りのあとで
笹原さんが箱根療養所を退所したのは、このパラリンピックから3年後の1967年6月のことだった。
パラリンピック後に厚生省は障害者の「社会復帰」を進めるようになり、箱根療養所の人々も前年の1966年から、これまで取得できなかった自動車免許を取れるようになった。免許の取得は療養所の方針でもあり、彼女も用意されたバスで教習所を行き来して免許を取った。
免許取得後の彼女が向かったのは、御殿場に作られた製造業の工場であった。
箱根療養所の入所者は10名ほどが一度にこの工場へ同時に就職しており、テレビのツマミをハンダ付けする仕事に従事した。
「ただ――」と彼女は言う。
「何しろ冬になると氷点下15度なんて日もある寒いところでしたからねェ。寮は4棟くらいあったけれど、こんな坂(と言って彼女は手を広げた)があるから雪が降ると外にも出られない。お風呂もシャワーだけで本当に寒かったの」
入所者を送り出した箱根療養所の医師たちも、さすがに不安だったのだろう。医師は週に一度の診察で寮を訪れていたが、彼女は「これは無理よ」と彼らに告げた。劣悪な住環境と慣れない仕事に体は耐え切れず、褥瘡ができて1年後には箱根療養所に再入所となってしまった。
だが、そうして再入所した療養所で彼女は同じ脊髄損傷の男性と出会い、しばらくして結婚することになった。よって御殿場の工場でのつらかった経験も、彼女のなかではそのために必要だった人生の経験として理解されているところがあるようだった。
彼女は結婚する1年前、夫と相談して御殿場の近くの小高い丘に土地を求め、車椅子でも生活のできる現在の家を建てた。小田原の大工に依頼して建築したその建物は、日本におけるいわゆる「バリアフリー住宅」の先駆けとなった。
「この家のスロープもトイレやお風呂も、みんな当時から変わっていないんですよ。それからはみんながしょっちゅう見学に来るようになってねェ。私は料理もできなかったけれど、練習して飯場の女将さんみたいになった。仲間がすごく増えたのよ。パラリンピックに行かなかったら、私は工場で働こうとは思わなかったでしょうし、まさか結婚しようとも考えなかったと思う。あのわずかな間に『やってみようかな』という気持ちになったのは、やっぱりパラリンピックに行ったから。あのとき、私は自分を試したいと本当に思ったの」
それが彼女の「1964年のパラリンピック」をめぐる物語であった。
【編集部よりお知らせ】
文藝春秋は、皆さんの投稿を募集しています。「#みんなの文藝春秋」で、文藝春秋に掲載された記事への感想・疑問・要望、または記事(に取り上げられたテーマ)を題材としたエッセイ、コラム、小説……などをぜひお書きください。投稿形式は「文章」であれば何でもOKです。編集部が「これは面白い!」と思った記事は、無料マガジン「#みんなの文藝春秋」に掲載させていただきます。皆さんの投稿、お待ちしています!
▼月額900円で『文藝春秋』最新号のコンテンツや過去記事アーカイブ、オリジナル記事が読み放題!『文藝春秋digital』の購読はこちらから!

