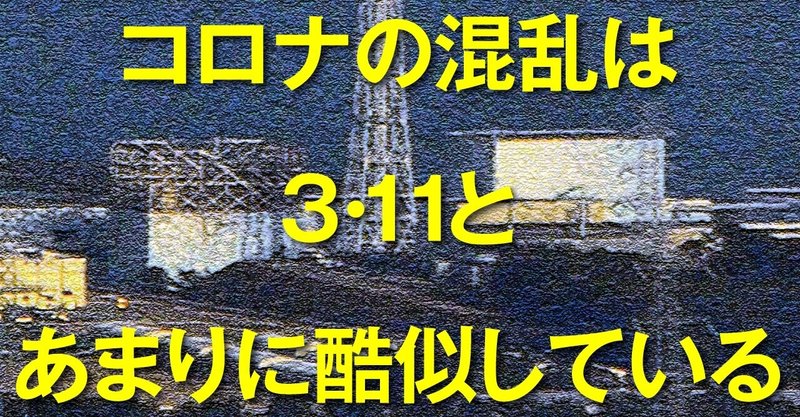
日本の敗戦「フクシマ」と「コロナ」——走り出したら止まれない“この国の病理”|船橋洋一
政治家も官僚も「有事」からただひたすらに逃走する──。コロナの混乱は10年前のフクシマとあまりに酷似している。/文・船橋洋一(アジア・パシフィック・イニシアティブ理事長)
<summary>
▶︎日本は国民の安全と健康に重大な危害を及ぼす脅威に対する「備え」に真正面から向かい合っていない、そして政府はそのリスクの存在を認識していながら、備えに真剣に取り組んでいない
▶︎「小さな安心を優先させ、大きな安全を犠牲にする」、いわば“安心ポピュリズム”とでもいうべき集団思考と空気が常態化してきた
▶︎コロナ禍において、日本は「デジタル敗戦」そして「ワクチン敗戦」という敗北を喫した

船橋氏
「備え」に真剣に取り組んでいない
フクシマとコロナの2つの危機は私たちに同じことを告げている。
日本は国民の安全と健康に重大な危害を及ぼす脅威に対する「備え」に真正面から向かい合っていない、そして政府はそのリスクの存在を認識していながら、備えに真剣に取り組んでいない、という点である。
福島第一原発事故の最大の教訓は、全交流電源喪失(SBO)などの原発の重大事故に対する備えをすること自体が住民に「不必要な不安と誤解を与える」という倒錯した論理の下、東京電力も原子力規制当局もそのリスクを「想定外」に棚上げし、備えを空洞化させた「絶対安全神話の罠」だった。実際、東京電力が地震と津波、なかでも津波に対する備えを怠ったことが命取りになった。
新型コロナウイルス感染症の場合も備えは不十分だった。検査体制も医療体制も増加する感染者の対応に追いつかなかったし、いまも追いついていない。それらの必要性は、2009年の新型インフルエンザ(A/H1N1)の後、設置された対策総括会議の報告書で指摘されていたにもかかわらず、政府はその後10年、それを放置した。
いずれの場合も、備え(prepared-ness)が不十分だったことが、危機の際の対応(response)の選択肢の幅を狭めた。有事の備えに対する政府の不作為、というその一点で両者は共通する。
コロナ危機において、私たちは再び、フクシマを戦っている。コロナの戦いの中でいまなお『フクシマ戦記』が繰り広げられている。

福島第一原発
訓練を見ると本気度がわかる
私は、福島第一原発事故の後、事故と危機の検証を行い、その後10年、当事者と関係者への取材を続けてきた。このほど刊行した『フクシマ戦記 10年後の「カウントダウン・メルトダウン」』(文藝春秋)がその報告だが、この間、何度もぶち当たったのが、なぜ日本は危機管理がこうも苦手なのか、どうして有事の備えに正面から取り組むことができないのか、というテーマだった。
たとえば、原子力災害に備えての訓練の本気度の欠如である。
福島原発危機の中で吉田昌郎所長が最も衝撃を受けた瞬間は、3号機建屋が爆発した後、総務班から「40人以上が安否不明」という報告を受けたときだった(後にそれは誤報だと知る)。「腹を切ろうと思っていた」と吉田は政府事故調の聴取で述べているが、ここで多くの死傷者が出た場合、その後の現場の対応はまったく異なる展開となっていただろう。
この点を質したところ、東電の幹部はこんな風に言った。
「私たちは兵士じゃないですから、隣でついさっきまで鉄砲を撃っていたやつがぱたっと倒れるという経験をしていません。そういう状況に置かれたときには激しく動揺しますよね。仲間を失った時でも平静を保てる訓練をしなければいけない。その部門は人を大幅に入れ替えなきゃいけないかもしれないし……」
福島の事故対応では、警察、消防、自衛隊がファーストリスポンダーとして現地に赴き、3号機の使用済み燃料プールへの放水作業を行った。政府が全力を挙げてプラント内で危機対応をしたことの意味は大きかったが、吉田所長が、自衛隊の放水を「セミの小便」と形容したように、実際、それらの放水作業の効果は疑問であった(もっとも、これらの放水の効果についての検証は行われていない)。ファーストリスポンダーのオンサイトでの作業の下準備や道案内のため1時間、2時間と現地で作業した東電の社員のほとんどが年間の緊急時線量上限の100ミリシーベルト以上被ばくした。放射性被ばくの法定限度に従えば、彼らはその後、現場で働けなくなってしまう。
福島原発事故から3年ほどしたころのことだが、新たに設置された原子力規制庁の幹部は、原発の事業者(電力会社)は「猫も杓子も電源喪失シナリオの下で訓練を行っている。想像力というものをまるで感じられない」と語ったものである。たしかに、電力会社は電源車にしてもバッテリーにしても防潮堤にしてもハード面では過剰なほど備えの手当をしてきた。しかし、「40人以上の仲間の死」に見舞われたときや線量過多で従業員が戦線を離脱しなければならないとき、のシナリオが訓練に組み込まれたという話は聞かない。危機のさなか、原子力安全・保安院の検査官たちは福島第一からオフサイトセンターに一方的に避難してしまったし、保安院はそれを黙認した。このような戦線離脱があったことも覚えておく必要がある。

自衛隊による福島原発への撒水作業
避難計画を再稼働の要件にせず
そもそも日本では、重大事故の際の住民避難をはじめ住民の安全確保のあり方(防災計画)について「政府一丸」と「社会一丸」で臨む態勢がいまなおできていない。原子力規制委員会は発足した後、「原子力災害対策指針」をまとめ、半径5キロ圏内を「予防的防護措置準備区域」(PAZ)、それより外側の半径30キロ圏内を「緊急時防護措置準備区域」(UPZ)とし、30キロ圏内の自治体には避難計画の策定を義務付けた。
実は、2012年6月に参議院環境委員会で原子力規制委員会設置法が可決された際、避難計画については「妥当性、実効可能性を確認する仕組みを検討すること」とする付帯決議がつけられた。これは「原発を動かすには、安全に逃げることのできる避難計画が必要だ。自治体に丸投げする仕組みでいいのか」との疑念を議員たちが抱いていたことを物語っている。
福島第一原発事故の教訓の一つは、直接の被ばくによる死でなく住民避難と防災の不整備による関連死が多かったことである。それだけに避難計画の「妥当性、実効可能性」を真摯に検討しなければならないはずなのだが、その双方とも心もとない。政府は「しっかりした避難計画が作れない中で再稼働を進めることはない」(菅義偉首相、衆院予算委員会=2020年11月4日)との立場を強調するが、法的には避難計画は再稼働の要件とされていない。
原子力規制委員会は「原子力災害対策指針」で30キロ圏の自治体に「地域防災計画」を策定するように義務付けたが、地方自治体は規制委員会が避難計画を再稼働の要件にしないことを“責任逃れ”と見て、不信感を表明した。政府は最終的に、発電所の事故対応(オンサイト対応)と避難対応(オフサイト対応)を分離させ、オンサイトは原子力規制庁が所掌し、オフサイトは内閣府原子力防災が調整することとした。この背景には、原子力規制委員会と規制庁が各省の総合調整を果たすのは難しいという判断があった。そこで内閣府原子力防災担当(大臣)を設置し、原子力防災の総合調整を担わせることにしたのである。
しかし、「実際問題として、あそこ(内閣府)では警察、消防、自衛隊を動員する執行力がないため、イザというときは杉田副長官にお願いすることを考えている」(政府幹部)のが実態である。安倍政権から菅義偉政権を通じて内閣官房副長官を務め、“危機管理の鬼”と言われる杉田和博官房副長官のことである。要するに、有事の際は法律通りには動かないだろうことを政府中枢が半ば認めているも同然なのである。

菅義偉首相
最悪のシナリオ「東京の住民避難」
菅直人首相(当時)は、危機が最も深刻になった2011年3月15日午前5時半過ぎ、東電本店に乗り込み、ゼッケン姿の社員たちを前に「命をかけてくれ」と絶叫した。国は原発事故に対応する実行部隊を持っていなかった。その日、東電に超法規的に対策統合本部をつくるまで事故対応の「司令塔」さえ不在だった。日本の政府は、有事における指揮命令系統、政府と地方自治体の間の権限と責任の位置づけ、ロジスティックス、コミュニケーション、法制度のいずれも不全かつ未熟だった。
ここから先は

文藝春秋digital
月刊誌『文藝春秋』の特集記事を中心に配信。月額900円。(「文藝春秋digital」は2023年5月末に終了します。今後は、新規登録なら「…

