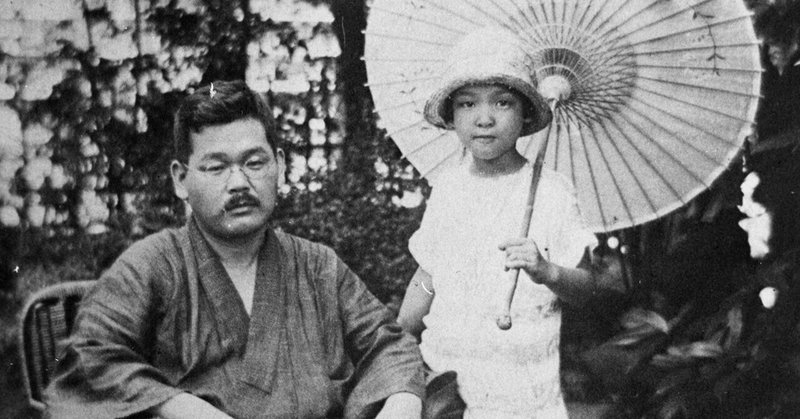
鹿島茂 ブルジョワ経営者 菊池寛アンド・カンパニー15
関東大震災で「文藝春秋」9月号は灰と化したが……
★前回を読む。
「文藝春秋」は、1月創刊号(3000部)から始まって、2月号(4000部)、3月号(6000部)と順調に部数を伸ばし、4月号でついに1万部の大台に乗ったが、それは同時に黒字化が達成された記念すべき号でもあった。すなわち、創刊号は89円(銭以下切り捨て)、2月号は6円、3月号は181円とそれぞれ赤字を出していたのが、4月号に至って71円の黒字に転じたのだ。定価を20銭にしたにもかかわらず、返本率が14パーセントにすぎなかったためである。
では、なぜこんなに細かいことがわかるかというと、8月号の末尾で菊池寛が「文藝春秋損益勘定」と題して、創刊号から4月号までの損益決算を発表しているからである。さらに「編輯後記」では、「これに依つて文藝春秋の經營の實際がよく分つたゞらうと思ふ」と書いているが、この損得勘定の公開は決算を公明正大に行うことで投資家の信頼を得るという欧米型の経営スタイルをよく理解していたためであり、そこに菊池寛の経営者としての近代性を見ることができる。
では、この決算報告書でわれわれは何に注目すべきかといえば、それは「支出之部」に計上されている「原稿料編輯費」である。つまり、菊池寛は創刊号で宣言した通り、有名・無名を問わず寄稿者に対しては原則的に原稿料を払っていたのである。これは当たり前のように思えるかもしれないが、出版界の常識では、現代でさえ「当たり前」ではない。いわんや、菊池寛のポケットマネーで創刊された雑誌である。やろうと思えば、無名作家に対しては「名前を売りたい」という熱情に、また有名作家には「友情」に、それぞれ付け込んで原稿料なしとしてもいいところだが、菊池寛は敢えてその安易な道を選ばず、原稿を書いたなら、たとえ少なくともギャランティーを払うのが当然という資本主義社会のまっとうな倫理に則って行動したのである。
もちろん、芥川や久米などの旧「新思潮」同人は「友情出演」だったようだが、これに対しても菊池寛は8月号の「編輯後記」でこう述べている。
「芥川その他の友人にも原稿料を拂はぬのは、本意でない。原稿料を拂ひ得るやうにしたいと思ふ。(中略)編輯者の本旨は、皆に無料で書いて貰ふことでなしに、皆に原稿料を充分に支拂ひたいことにある」
この一文からもわかるように、菊池寛はプロレタリア作家が非難したような意味ではなく、等価交換を道徳とする正しい意味での「ブルジョワ経営者」だったのである。この意味は決して小さくない。

溌剌とした作品ぞろい
そして、このブルジョワ経営者は、成熟しつつある大正末の大衆社会が何を求めているのかを正確に読み取っていたので、5月号から新手の編集方針をいくつか打ち出していた。
ここから先は

文藝春秋digital
月刊誌『文藝春秋』の特集記事を中心に配信。月額900円。(「文藝春秋digital」は2023年5月末に終了します。今後は、新規登録なら「…

