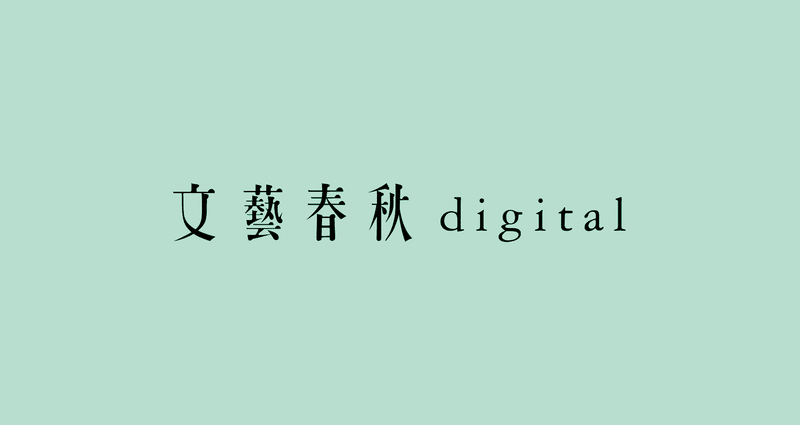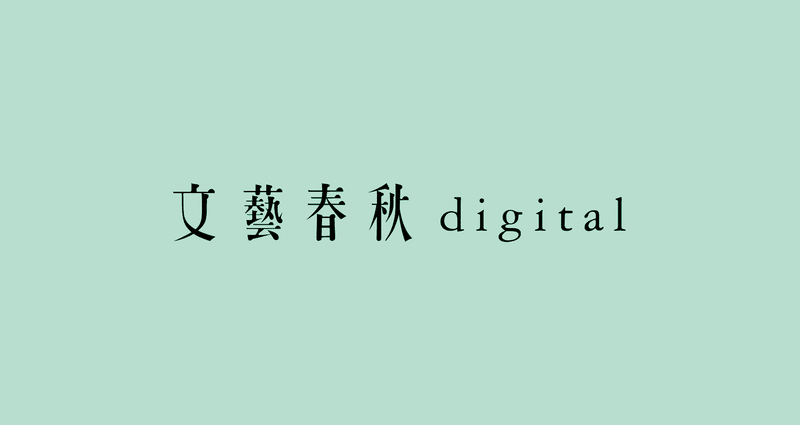みのもんた、テレビ引退宣言! 「でも銀座はやめられないね」
みのもんた(本名・御法川(みのりかわ)法男)は、1944年生まれ。立教大学経済学部を卒業後、1967年に文化放送に入社。ラジオ番組「みのもんたのセイ!ヤング」などの担当を経て、1979年にはフリーに。1989年から司会を担当した情報番組「午後は○○おもいッきりテレビ」(日本テレビ系列)で人気を確立し、2006年には「1週間で最も多く生番組に出演する司会者」としてギネス世界記録に認定された。自身の個人事務所を兼ねる水道メーター製造・販売会社「ニッコク」の代表取締役社長も務める。