
原子力活用を一歩前へ! 西村康稔
エネルギー政策の転換は待ったなし。「再エネ一本足打法」では危うい
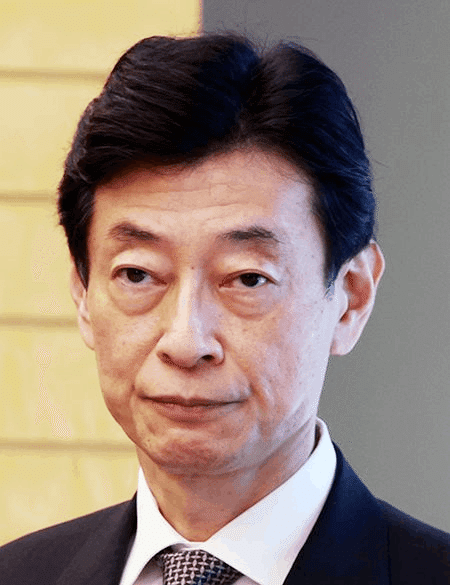
西村氏 ©時事通信社
「三つの危機」
東京・霞ヶ関。経済産業省11階の大臣執務室の片隅に、一枚の写真が飾られている。
ドイツのメルケル首相が身を乗り出すように両手を机に置き、反対側に座るトランプ米国大統領をじっと見つめる。その後ろには、腕を組んで両首脳を見つめる安倍晋三内閣総理大臣―――。2018年、カナダのシャルルボアで開かれたG7サミット会場の一場面を捉えたスナップ・ショットだ。世界中に配信されて一躍有名になったこの一葉の写真には、総理の左隣に、官房副長官として会議に同行した私も小さく映り込んでいる。生前の安倍元総理には「西村くんだけはカメラ目線だよね」などと冗談を言われたものだ。
合意文書の細かな文言一つ一つを巡って激論を続ける各国首脳の間に割って入り、G7の結束のため、自由で公正な貿易の重要性を説き、堂々と自らの意見を述べる安倍総理の雄姿は、実に頼もしいものだった。各国首脳も「シンゾーがそういうのならば」と言って矛を収めてくれる場面を何度も目撃した。私は、官房副長官として安倍総理の外遊に何度も同行しただけでなく、その後も、TPP担当大臣として、安倍外交の舞台裏を垣間見てきた。そこに通底していたのは、徹頭徹尾、日本の国益を断固として守っていく、という揺るぎない決意であったように思う。
それから数年を経て、国際情勢はさらに混沌を深めている。新型コロナ、ウクライナ戦争、そして気候変動と、三つの危機が同時進行中である。今こそ、地球儀を俯瞰する安倍外交の遺産を継承して、世界情勢の激動を的確に読み解き、この「三つの危機」に同時対応しながら、将来の日本の見取り図を明確に描いていかなければならない。
エネルギー政策は「天命」
その際に、守られるべき国益とは具体的に何なのか。その最たるものが、エネルギーの安定供給の確保であろう。気候変動への対処も待ったなしの課題となっている今、イノベーションを通じて、いかにして脱炭素社会への転換を進めていけるのかもまた、国全体の競争力を左右する死活的な課題となっている。そして、ロシアによるウクライナ侵略によって、資源価格は高騰し、世界各国に新たな試練を課している。カーボン・ニュートラルの実現という高い目標を競い合い、足下で対露制裁を巡って繰り広げられる様々な駆け引き。その裏側に垣間見える本質は、各国の国益を賭けた「エネルギー争奪戦」ともいうべき、むき出しの国家間競争に他ならない。
四方を海で囲まれた島国日本は、残念ながら、資源に恵まれない国である。狭い国土に平地も少なく、資源の大半を海外に依存しながら、膨大なエネルギーを消費している。原油について言えば、約95%を中東に依存しており、LNGは全体の9%程度がロシアからの供給だ。エネルギー安全保障上の観点からは、日本企業が権益を持つサハリン1・2の重要性は変わらない。言うまでもなく、エネルギーの安定供給は、暮らしにとっても、経済にとっても、何よりも重要なのである。
そうした中で、エネルギーの安定供給を重要な使命の一つに数える経済産業大臣としての職責は、以前にも増して重い。そして、前任の萩生田光一大臣から引き続き、「GX(グリーントランスフォーメーション)実行推進担当大臣」を拝命した。エネルギー政策の舵取りは、単に狭義の「エネルギー」の領域に留まらず、この先の経済社会、産業構造の大変革が求められる、重大な職責である。
幸いにして私は、これまでの職業人生を通じて、エネルギー・環境問題への関わりをライフワークとしてきた。政治の世界に身を投じる前も、通商産業省(現・経済産業省)で15年間を役人として過ごす中で、半分くらいのキャリアはエネルギー・環境関連の政策に携わってきた。京都議定書やパリ協定の出発点となる「気候変動枠組条約」を採択した1992年のリオ地球サミットの現場にも、留学先の米国から駆けつけた。国会議員となってからも、エネルギー・環境との関わりは続いた。役人時代の中東との関わりをきっかけに、サウジアラビア、オマーン、アラブ首長国連邦(UAE)、イランといった中東各国とのネットワークが広がり、議員連盟の会長なども務めてきた。各国のエネルギー担当の閣僚や在京の大使たちとは、今でも親しくさせていただいている。東日本大震災の後には、再生可能エネルギーの大量導入を後押しするための再生可能エネルギー買い取り法案、いわゆるFIT法案の議員修正プロセスを主導し、事故を起こした東京電力の巨額の賠償をまかなうための原子力損害賠償支援機構法案の審議にも深く関わった。いずれも今に至るエネルギー・原子力政策の中核となっている法的な枠組である。
若き日に青春を賭けた政策課題に、時代の転換点となるいま、再び関わることとなったのは、少し気取った言い方をすれば、ある種の「天命」だと感じる。エネルギー・環境政策は、複雑な方程式を解くような難しさがあり、実務的な課題がどういう点にあるかをよく見極めなければ、適切な政策を進めていくことは難しい。これまでの経験から、細かな論点に通じ、現場目線での想像力を働かせることができるのは、私の一つの強みではないかと考えている。

サハリン2には三井物産が出資 ©時事通信社
「安定供給の方程式」が崩れた
11年前の東日本大震災と福島第一原発事故は、我が国のエネルギー政策に、今もなお大きな傷跡を残している。石油ショック後の日本で、純国産のエネルギー多角化の切り札として導入が拡大した原子力発電は、事故前には国内の電力供給の3割近くを担っていたが、事故により順次稼働が止まり、一時期はゼロとなった。半世紀近く前から先人たちが築いてきた「安定供給の方程式」は崩れてしまったのだ。
東日本大震災の後、自由化と競争をベースにした電力・ガスの新たな制度を構想し、その実現を目指してきた。電力会社の供給区域を越えて、電力を全国規模で融通する仕組みを整え、新たなプレイヤーの参入で新しいサービスメニューも生まれた。改革の成果は確かに生まれている。ただし、改革は、まだまだ道半ばにある。とりわけ問題となるのが、結果として、足元の電力が綱渡りの状態となってしまっていることだ。
背景には、様々な要因がある。電力自由化を進める中で、本来であればセットで実施すべき発電を増やすための制度措置の整備が遅れ、国際的な脱炭素の流れを背景にした再生可能エネルギーの急速な導入もあって、採算が取れない火力発電の休廃止が急増してしまった。予期せぬ自然災害で供給力が一時的に低下し、季節外れの暑さ寒さで需要が上振れしたという面もある。
この夏は、国民の節電への協力で何とか乗り切ることができた。しかし、電力需要が季節的にも大きい次の冬は、安定供給に最低限必要な水準である3パーセントの予備率を何とか上回っているものの、依然として厳しい状況にある。また、停止した原発の分を火力発電で代替している中で燃料価格が高騰し、再生可能エネルギーの導入に伴う負担も増加した。そのため、電気料金はじりじりと値上がりしている。
低廉で安定的な電力供給の両立という古くて新しい課題は、これまでの取組の抜本的見直しを迫っている。エネルギー政策の再構築は、待ったなしの課題なのだ。
原発は「実証済み」の脱炭素技術
エネルギー政策を進める上での最も重要な考え方は、現実主義の発想である。安定供給を確保するためには、なるべく手持ちのカードを多く持ち、持てる選択肢はすべて最大限に有効活用しなければならない。
2050年のカーボン・ニュートラルを目指す以上、再生可能エネルギーの最大導入に取り組むことは論を俟たない。しかし、気象条件に左右される「再エネ一本足打法」では、安定供給の確保は危うい。
もちろん、太陽光も洋上風力も地熱も、革新的な技術開発も含め、あらゆる可能性を探求し、どこまで行けるか突き詰めてみるべきだ。大型蓄電池技術の革新にも挑戦が必要だ。また、火力発電の燃料を徐々に水素やアンモニアに置き換え、CCUSという二酸化炭素の地下貯留、利用を組み合わせる、「ゼロエミッション火力」への転換も重要である。北海道の苫小牧でCCS(二酸化炭素回収・貯留)の実証試験が成功したが、いまだ石炭火力に依存するアジアの国々との関係でも将来の一つのモデルとなりうる。
国際的なサプライチェーンの構築という面からは、水素も日本企業が世界をリードしている。神戸の川崎重工の工場で、世界初の液化水素運搬船を視察したことがある。オーストラリアと日本の間で、既に実証事業として海上輸送が行われている。水素をトルエンに付加して効率よく運ぶMCHという取組も進んでいる。東京電力と中部電力が共同出資したJERAの碧南火力発電所でアンモニアを混焼する実証事業の現場も視察した。
ただし、こうした革新的な技術は、内容が革新的であればあるほど、実現へのハードルは決して低いものではなく、相当な時間もかかる。どこまでいっても、一定の不確実性があることを想定の中に織り込まなければ、エネルギー政策を司る立場からは無責任のそしりを逃れられない。
そう考えていくと、既に実用化され、実証された技術には一日の長がある。東日本大震災前に日本の電力の3割近くを担った実績のある原子力は、運転時には温室効果ガスを排出しない、まさに「実証済み」の脱炭素技術である。ベースロード電源として安定的に電力を供給でき、わずかなウラン燃料で数年間の運転を続けられることから「準国産エネルギー源」とされる。ウランは有志国から安定的な調達が期待できる。脱炭素化と脱ロシアのダブル転換を進める欧米各国では、「原子力」という技術の選択肢を改めて吟味しようとする動きが出てきている。
さらに原子力は、エネルギー安全保障に寄与する貴重な電源の一つでもある。世界的なエネルギー価格の高騰が定着しつつある中、原子力の活用は、資源を持たざる国の経済的な弱点を補完する効用も期待できる。脱炭素化とエネルギー安全保障の両立を本気で進めるべく、日本でも、今こそ、原子力の更なる活用に向けた真剣な検討を一歩先に進めるべき時ではないだろうか。
総力を結集してまずは再稼働
7月27日、岸田文雄総理は第一回のGX実行会議の場で、電力・ガスの安定供給に向けて、再エネ・蓄電池・省エネの最大限導入のための制度的支援策や、原発の再稼働とその先の展開策など具体的な方策について、政治の決断が求められる項目を明確に示すよう指示をされた。
8月の第二回会合で、GX実行推進担当大臣の私からは、原子力に関しては、(1)再稼働への関係者の総力の結集、(2)安全第一での運転期間延長、(3)次世代革新炉の開発・建設の検討、(4)再処理・廃炉・最終処分のプロセスの加速化という4点を挙げた。年内に結論を出せるよう、与党や専門家の意見も踏まえて、検討を加速することとしている。いずれの検討課題も、原子力規制委員会により安全性が確認されなければ、原発の運転ができないという現行の仕組みを維持することが大前提である。
1つ目の再稼働については、震災前に54基あった日本国内の稼働中の原発は、東日本大震災の後、一旦はすべてが稼働を停止した。事故を起こしてしまった福島第一原発の6基に加え、経済性の面などから廃炉が決まった原発もあり、残っているのは36基である。独立した原子力規制委員会によって、新たな規制基準に基づき安全性が確認された原発は、地元の理解を得ながら再稼働を進めていく。その大方針に則って、現在までに10基が再稼働に至った。
この「10」という数字は、評価が分かれるかもしれない。足下で原子力は国内総発電量の4パーセントほどを発電しているに過ぎず(2020年度)、震災前と比べれば、原子力への依存は実態として大きく下がっている。だが、政府としては、2030年の電源構成のうち、20から22パーセントを原子力でまかなうとの目標を設定している。これに関して言えば、既存原発の再稼働のみで充分に達成可能な数字だ。
将来の選択肢を残す
2点目の、原発の運転期間の扱いも重要な論点の一つである。東日本大震災直後の経緯で、科学的な安全性審査とは異なる観点から、40年間の運転期間を一度に限り20年延長するという制度ができあがった。しかし、例えば、再稼働していない東日本の原発であれば、10年以上も燃料を装填せず、原子炉は停止したままとなっている。原子炉が中性子で劣化せず、安全上は問題ない場合であっても、「40年」の時計の針が進んでしまうという課題も指摘されており、こうした「ロスタイム」の扱いなど、利用政策の観点から、何らかの見直しが必要だという議論が審議会で始められている。
ここから先は

文藝春秋digital
月刊誌『文藝春秋』の特集記事を中心に配信。月額900円。(「文藝春秋digital」は2023年5月末に終了します。今後は、新規登録なら「…

