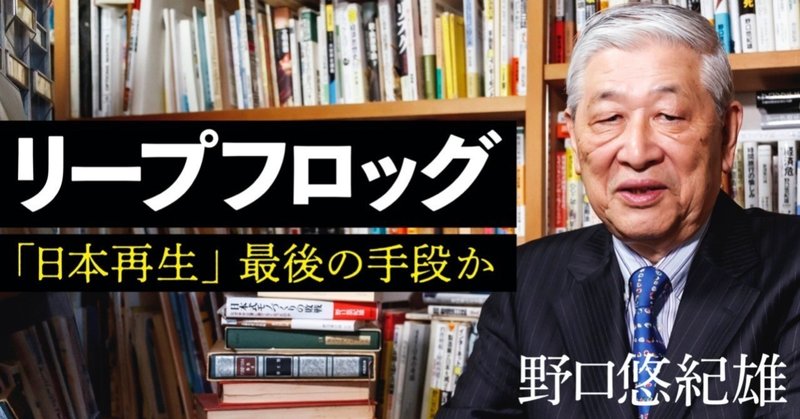
中国でリープフロッグが起きたのはなぜか?/野口悠紀雄
★前回の記事はこちら。
※本連載は第10回です。最初から読む方はこちら。
中国成長の謎を解く鍵は、リープフロッグにあります。これは、「後れていたから飛び越えた」ということです。
ただし、単に後れていただけでなく、改革開放とインターネットの登場がほぼ同時だったこと、国営企業の改革で既得権を整理していたこと、などの条件がありました。
◇中国は、後れたから、先に行けた
これまで述べてきたことを、まとめましょう。中国では、eコマースが成長し、電子マネーによるキャッシュレス化が進んでいます。
AI(人工知能)による顔認識機能を利用した決済も導入され、無人店舗が広がっています。
また、電子マネーの利用履歴から得られるデータを利用した信用スコアなどの新しいサービスも始まっています。
このように、最先端分野における目覚しい発展が実現されています。
固定電話が普及していなかったために、新しい通信手段であるインターネットやスマートフォンが急速に普及し、それがこのような発展をもたらしたのです。
また、これまで中国では、信用供与のシステムが確立されていなかったことなど、市場経済の基本的なインフラストラクチャーがありませんでした。このため、人々が信用スコアリングや顔認証等を受け入れたという面があります。
結局のところ、中国は、「後れていたために新しい技術を取り入れることができた」ということができます。
これが「リープフロッグ」と言われる現象です。
中国が先端技術で最先端を走っているのは、このメカニズムによるところが大きいのです。
「後れていたことを逆手に取った」ということができますし、「失敗したから成功した」ということもできます。
リープフロッグ現象は、これまでも、歴史上さまざまな場面で見られました。しかし、これほど大規模に起きたのは初めてのことといえます。
◇ビルは更地に建てる方が簡単
「破壊的技術」と言われるものがあります。
これは、それまでの技術体系が形成していた産業構造や社会構造を広範に破壊するほど大きな影響力を持つ新技術です。
インターネットは、破壊的技術の典型的なものです。
これまで、様々な産業を破壊してきました。
例えば固定電話のシステムを破壊しました。
この過程で社会的な摩擦が生じることは避けられません。
逆に言えば、日本やアメリカで、仮に電話が存在しなかったとしたら、インターネットはもっと急速に普及していた可能性があります。
中国において起こったのが、まさにそれです。古い通信技術に束縛された経済・社会構造になっていなかったために、発展したのです。
生産性向上のために、新しい技術の導入が必要であると言われます。しかし、古い技術で経済・社会の体系が作られてしまうと、それを新しい技術に対応させるのは難しいのです。既得権益者がいるために、経済効率の悪い古い技術が使われ続けることになります。
これは、高層ビルを建築する場合に、既成市街地よりは新開発地のほうが簡単であるのと同じことです。
既成市街地の住宅密集地にビルを建てるには、まずそこを更地にする必要があり、このためには、多大な費用が必要になるからです。
日本で既成市街地がなかなか高層化できないのは、(地震が多いというような自然条件によるのではなく)、このような理由によります。
そうした条件に縛られない中国の大都市では、高層ビルが林立しています。
◇たまたまタイミングがあった
ただし、実際に起きたことは、もっと複雑です。
中国で大規模なリープフロッグが起きたのは、単に中国が後れていたからだけではありません。
タイミングがうまくあったのです。
つまり、「改革開放による近代化と、新しい情報技術の登場が、たまたま同時に起きた」という幸運があったのです。
仮に改革開放に転換したのが1960年代だったとすれば、固定電話のために膨大な投資が行われたでしょう。また、後れている流通システムの近代化のために、商店網の建設がなされ、膨大な投資が行なわれたでしょう。
それらの投資は、後から見れば、無駄な投資だったことになります。
中国の場合、資本蓄積のための国内貯蓄はきわめて少なかったので、こうした投資のために膨大な海外からの借り入れが必要になったはずで、それは中国の発展の足かせになったでしょう。
産業構造の面では、労働集約型製造業が目指されたと考えられます。
豊富な労働力が存在したため、これは成長したでしょう(実際に、2010年頃までの中国の経済成長は、このパターンが中心だったのです)。
しかし、それでは、日本や韓国など、より早く工業化した国を追うだけのことに終わったはずです。
また、インターネットが利用可能になっても、社会主義経済のままでは採用できなかったでしょう。
事実、ソ連では、ファックスが技術的に利用可能になったときも、この利用を禁止したのです。
結局の所、中国では、インターネットの登場と工業化が同時化したために、さまざまな面でリープフロッグが起きたのです。
◇国営企業の改革によって、既得権が整理された
ところで、中国で既得権がなかったわけではありません。
社会主義経済体制は確立されていたわけで、そこには強固な既得権が存在しました。
とくに国営企業がありました。
1978年の第11期中央委員会第3回全体会議(三中全会)において、鄧小平が「改革開放、現代化路線」を掲げて政策を大転換させ、これによって「改革開放」が中国の基本路線となりました。
しかし、当初は、改革開放は政治の世界で言われていただけであり、経済の実態が大きく変わるには至りませんでした。それは、膨大な数の公的企業があり、これらが非効率的な経済活動を行っていたためです。
1990年代半ば頃から、「抓大放小」(大をつかまえ小を放す)という方針に従って、国有企業の改革が行われました。
これは、基幹産業の大企業は国家が所有するが、中小企業は民営化するという方針です。
中小国有企業の民営化は、経営者が自社を買収して独立することを通じて行なわれました。
大型国有企業についても、政府は1990年後半以降、上場を推進しました。
そして、1998年に、経営不振の国有企業の破綻処理と、レイオフを通じた大規模な人員削減を実施したのです。
90年代の後半から2000年代の初期にかけて、数万に及ぶ国有企業が閉鎖され、約3000万人が職を失い、民間企業に就職しました。
この改革は、極めて面倒なことであったと考えられます。
しかし、それによって、社会主義時代の既得権益は整理されたのです。
◇自由な活動が認められたから、リープフロッグできた
従来、中国ではすべての産業が国家によって運営されていましたが、そのうち基幹産業の大企業については、国家が保有した上で株式会社として上場を推進するという改革がおこなわれました。
そして、それ以外の企業については、民営化が進められました。これによって、消費財部門は民営化されました。
このため、IT関連のスタートアップ企業が誕生したのです。
通信機器の分野では、1988年に華為技術(ファーウェイ・テクノロジーズ)が設立されました。
インターネットでは多数のベンチャー企業が誕生しました。阿里巴巴集団(アリババ・グループ)や百度(バイドゥ)はよく知られています。
これらは、それぞれ、AmazonやeBayとGoogleの中国版ですが、その他のネットサービスでも、アメリカのサービスと同じものを中国のベンチャー企業が提供するようになりました。
これらの新しい企業は、強い規制に制約されることはなく、新しいビジネスを自由に展開していくことが可能だったのです。
このように、中国は、決して最初から更地であったわけではありません。「努力して更地にした」という面があったのです。
ここで注意すべきは、これらのベンチャー企業を政府が積極的に支援したわけでないことです。自由な環境を整えたという点が重要なのです。
◇中国は行き過ぎているかもしれない
リープフロッグは、中国を発展させました。しかし、いいことばかりではありません。
AIによるプロファイリングに抵抗がないのは、それまでの中国で、信用を測る方法が確立されていなかったためです。
リープフロッグによって信用スコアリングが導入され、信頼に基づく取引が可能になったわけですが、そのメリットが過大評価されている可能性があります。
しかし、ここには、プライバシーの犠牲という重大な問題があることに注意が必要です。
そして、中国では、こうした個人情報が、政府による国民の管理に用いられる危険があります。
これは、中国の将来に対して、きわめて重大な問題を提起しています。
(連載第10回)
★第11回を読む。
■野口悠紀雄(のぐち・ゆきお)
1940年、東京に生まれる。 1963年、東京大学工学部卒業。 1964年、大蔵省入省。 1972年、エール大学Ph.D.(経済学博士号)を取得。 一橋大学教授、東京大学教授(先端経済工学研究センター長)、 スタンフォード大学客員教授などを経て、 2005年4月より早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授。 2011年4月より 早稲田大学ファイナンス総合研究所顧問。一橋大学名誉教授。2017年9月より早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター顧問。著書多数。
【編集部よりお知らせ】
文藝春秋は、皆さんの投稿を募集しています。「#みんなの文藝春秋」で、文藝春秋に掲載された記事への感想・疑問・要望、または記事(に取り上げられたテーマ)を題材としたエッセイ、コラム、小説……などをぜひお書きください。投稿形式は「文章」であれば何でもOKです。編集部が「これは面白い!」と思った記事は、無料マガジン「#みんなの文藝春秋」に掲載させていただきます。皆さんの投稿、お待ちしています!
▼月額900円で月70本以上の『文藝春秋』最新号のコンテンツや過去記事アーカイブ、オリジナル記事が読み放題!『文藝春秋digital』の購読はこちらから!

